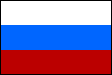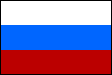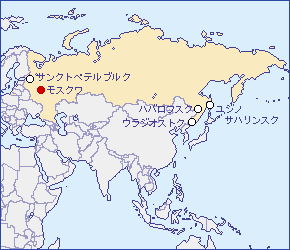ロシア
ロシアの基本情報
- 最終更新
- 2007-04-21T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/rossiya/rus.html#basic
- 国・地域名(ISO 3166-1による英語名)
- ロシア連邦【Russian Federation】。公式の英語表記は、Russian Federation。
- 首都
- モスクワ【Moskva(Moscow)】
- 国旗
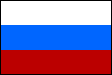
- 人種
- ロシア人79.8%、タタール人3.8%、ウクライナ人2.0%、バシキル人1.1%、チュバシ人1.1%等
- 言語
- 100以上の言語があるが、ロシア語が公用語。ただし、連邦構成主体の各共和国は連邦公用語(ロシア語)とは別に、自らの公用語を定めうることが憲法で認められている。
- 宗教
- ロシア正教が最も優勢であるが、多民族国家を反映してイスラム教、仏教、ユダヤ教等多数の宗教が混在。
- 通貨
- ルーブル:Ruble(RUB)
- 3文字国名コード/2文字国名コード/数字国名コード
- RUS/RU/643
- 人口/面積
- 143,782,338人/17,075,200平方キロメートル(日本の45倍、アメリカ合衆国の2倍近く)
- 国歌/国花/国鳥
- ロシア連邦国歌/-/-
- 漢字による表記
- 露西亜/露矢亜/露国/魯西亜
- 時間帯
- UTC +2 〜 +12(DST: +3 〜 +13)
- ccTLD
- .RU
- 国際電話番号
- 7
ロシアのその他情報
- 最終更新
- 2007-10-02T19:05:05+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/rossiya/rus.html#other
ロシアの地形
ユーラシア大陸の北部にバルト海沿岸から太平洋まで東西に伸びる世界最大の領土を持つ連邦制の共和国。北西から順にノルウェー、フィンランド、エストニア、ラトビア、ベラルーシ、リトアニア、ポーランド(ポーランドとの国境はバルト海とリトアニアに囲まれた飛び地領カリーニングラード州)、ウクライナ、グルジア、アゼルバイジャン、カザフスタン、中国、モンゴル、北朝鮮と国境を接する。国土を囲む海域には、北極海の一部であるバレンツ海、白海、カラ海、ラプテフ海、東シベリア海と、太平洋の一部であるベーリング海、オホーツク海、日本海、そして西のバルト海と西南の黒海があり、海岸線は37,000kmに及ぶ。これらの海に浮かぶロシア領の主要な島には、ゼムリャフランツァヨシファ、ノヴァヤゼムリャ、セヴェルナヤ・ゼムリャ諸島、ノヴォシビルスク諸島、ウランゲル島、サハリン(樺太)、クリル諸島(千島列島)。国土の北辺は北極圏に入り人口も希薄だが、南辺に近づくと地理的に多様となり人口も多くなる。ヨーロッパ部とアジア部(シベリア)の大部分は広大な平原で、南部のステップから北は広大なタイガがその大部分を占めており、さらに高緯度になると、樹木の生育しないツンドラ地帯となる。黒海とカスピ海の間の南の国境にはヨーロッパ最高峰のエルブルス山を含むカフカース山脈があり、ヨーロッパとロシアの境界にはウラル山脈がある。ロシア領内の主要な川には、ヨーロッパ部のドン川、ヴォルガ川、カマ川、オカ川、アジア部のオビ川、エニセイ川、レナ川、アムール川などの大河があげられる。また、ブリヤート共和国のバイカル湖は世界一古く水深の深い湖として有名な構造湖である。
ロシアの気候
北からツンドラ気候、寒帯気候、冷帯気候、温帯ステップ気と変化するが、一般に寒冷で東に進むほど年較差の大きい大陸性の特色が強くなる。ヨーロッパロシアの南部は温和だが、東シベリアは人間が居住する地域では世界の最寒地とされる。植生は、北からツンドラ、タイガ、混合林、プレーリー、ステップ。西部では混合林、東部ではタイガの比率が高い。
ロシアの経済
世界最大の国土を抱え、熱帯性を除くあらゆる農産物を生産、特に穀物生産量が多い。しかし厳しい気候の影響もあって生産が不安定で、輸入に依存することもある。農場の多くは今も国営農場や集団農場で、民営化のペースは遅い。食肉供給が不足していたこともあり、水産物の消費量は多い。大西洋、北極海、太平洋のいずれでも大規模な漁業が行われ、漁獲量は世界有数。地下資源は極めて豊富で、鉱物、化石燃料、宝石を産する。特に石油と天然ガスは戦略的な輸出物資であり、政府がコントロールしている。その他燃料に用いられる亜炭、石炭の採掘量も多い。工業はソ連時代の計画経済により、重化学工業と軍需産業を中心に急速に発展。しかし民生用のハイテク産業や消費財産業等は先進工業諸国に較べ遅れている。1998年には金融不安からルーブルが大きく下落し、海外からの投資は低迷、世界経済にも大きな打撃を与えた。その後原油価格や資源価格が上昇したことで、貿易収支が改善、経済成長もプラスに転じた。
主要貿易品目
輸出は石油、天然ガス、鉄、非鉄金属、機械設備等。輸入は機械設備、食料品、農産物等。
主要貿易相手国
ドイツ、オランダ、イタリア、中国、ウクライナ、ベラルーシ、アメリカ。
ロシアの歴史
- 862年:ノルマン人首長リューリクがノヴゴロドの公となり、その一族が東スラヴ人の居住地域に支配を広げていく過程で、ロシアとウクライナ・ベラルーシの原型である中世のルーシ地域が形成される。当初のルーシの中心は、現在はウクライナの首都であるキエフ。
- 13世紀初頭:モンゴルによって征服され、キプチャク・ハン国の支配下に入る。
- 1380年9月15日:モスクワ大公ドミトリー・ドンスコイが指揮するロシア諸公軍とタタール軍とが激突。モスクワが初めてタタールに勝利(クリコボの戦い)。
- 15世紀:イワン4世(雷帝)の時にモスクワ公は、モンゴル支配下でルーシ諸公がハンに納める貢納を取りまとめる役を請け負うことで次第に実力をつけ、キプチャク・ハン国の支配を実質的に脱してルーシの統一を押し進める。
- 1547年1月16日:イワン雷帝、ロシア初の専制君主となる。
- 1613年:ロマノフ朝が成立。
- 1689年9月7日:清国と国境画定の為の「ネルチンスク条約」に調印。
- 18世紀、ピョートル1世(大帝)は急速な西欧化・近代化政策を強行し、新首都サンクトペテルブルクの建設(1703)、大北方戦争(1700〜1721)での勝利を経てロシア帝国の基盤を築く。
- 1762年6月29日:ドイツに生まれ、ロシア皇太子妃となったエカテリーナ2世が、皇帝となった夫を退けて自らが女帝の地位に(無血革命に成功)。
- 1812年:ナポレオン・ボナパルト指揮のフランス軍に侵攻されたが、大損害を負いながらこれを撃退。
- 1812年10月19日:ナポレオンのフランス軍がロシアからの退却を開始。
- 1813年10月17日:プロイセン・オーストリア・ロシア連合軍がナポレオン軍に大勝(ライプチヒの戦い)。
- 1830年11月29日:ロシア皇帝ニコライ1世がフランスの七月革命鎮圧のためにポーランド軍を動員しようとしたのに対し、ワルシャワで士官が反乱。市民がこれに呼応し武器庫を占領(11月蜂起)。
- 1833年7月8日:ロシアとトルコが「ウンキャル・スケレッシ条約」に調印。ロシアのダーダネルス・ボスポロス両海狭の自由航行が認められ地中海への出口を確保。
- 19世紀後半:南下政策を推し進め、これによってトルコ等周辺国と戦争を引き起こし、イギリスとの対立が激化。
- 1853年10月16日:クリミヤ戦争勃発(ロシア軍がトルコ支配下のドナウ諸公国に進駐したため、トルコがロシアに宣戦布告)。
- 1853年:クリミア戦争でイギリス・フランスに惨敗。
- 1861年:皇帝アレクサンドル2世は農奴解放令を発布。
- 1869年6月24日:ロシア兵が樺太函泊を占領。
- 1871年7月4日:ロシアが中央アジアの清国領・イリ地方に出兵し占領(イリ事件)。
- 1872年9月6日:ベルリンでドイツ・オーストリア・ロシアの皇帝が会談。三帝同盟を結成。
- 1873年10月22日:フランスに対抗するため、ドイツのヴィルヘルム1世、オーストリアのフランツ・ヨーゼフ1世、ロシアのアレクサンドル2世が三帝同盟を結成。
- 1900年12月7日:アラスカのユーコン川流域で金鉱が発見される。
- 1902年10月8日:ロシアが清国との満州還付条約に基づいて第1期満州撤兵を開始。
- 1903年10月8日:ロシア軍が奉天省城を占領(満州還付条約にもとづく第3次満州撤兵を不履行)。
- 1904年7月20日:ウラジオストク艦隊が津軽海峡を通過(青森県・磯谷沖で東京汽船の高島丸を、太平洋岸で汽船・帆船など5隻を撃沈)。
- 1904年7月21日:モスクワとウラジオストクを結ぶシベリア横断鉄道が完成。
- 1904年7月26日:旅順攻囲軍が攻撃を開始(日露戦争)。
- 1904年8月1日:日本軍が海城を占領(日露戦争)。
- 1904年8月10日:ロシア艦隊が旅順を出撃して黄海で交戦するが、連合艦隊がロシア艦隊を撃破しロシア軍主力は旅順に敗走(黄海の海戦:日露戦争)。
- 1904年12月5日:日本軍がロシアの難攻不落の要塞「二〇三高地」を占領(日本軍の死傷者は1万6935人、翌日から旅順内のロシア艦隊を砲撃し旅順艦隊は全滅:日露戦争)。
- 1905年1月1日:ロシア軍が旅順で降伏(日露戦争)。
- 1905年1月16日:ロシア・ペテルブルグの工場でスト開始(血の日曜日の発端に)。
- 1905年7月7日:日本軍・第13師団が南樺太に上陸(8日には大泊を占領し、24日北樺太に上陸を開始:日露戦争)。
- 1905年7月11日:ロシアのニコライ2世が(日露戦争の)講和条件を認可(19日にロシア全権のウィッテ・ローゼンがポーツマスヘ出発)。
- 1905年7月31日:樺太のロシア軍が降伏し、日露戦争が終結。
- 1905年:首都ペテルブルクで軍隊が労働者のデモ隊に発砲。死者千人以上(血の日曜日)。ロシア革命の契機に。
- 1905年6月27日:黒海艦隊の戦艦ポチョムキンの反乱。
- 1905年8月19日:ロシア革命で皇帝ニコライ2世が国会開設を告示。
- 1905年10月26日:ロシアのペトログラードで労働者・兵士代表による評議会「ソビエト」を結成。
- 1905年10月30日:ロシア革命でニコライ2世が国会開設・憲法制度などを宣言(10月勅令)。
- 1912年7月8日:第3回日露協約が調印される(蒙古での特殊利益を相互に承認し、東側を日本のもの西側をロシアのものとする秘密協定のみ改定)。
- 1914年8月1日:第1次大戦で、ドイツがロシアに宣戦布告。
- 1914年:第一次世界大戦では連合国の一員としてドイツ、オーストリアと開戦、敗北を重ねて領土深くまで侵攻される。
- 1914年10月30日:第1次大戦で、ロシアがトルコに宣戦布告。
- 1915年11月30日:日・仏・英・伊・露の5か国が単独不講和宣言に調印。
- 1916年7月3日:日本とロシアが大正5年協約・第4次日露協約に調印(支那が第3国の支配下におかれるのを防ぐため秘密協定で協力を規定)。
- 1916年12月29日:帝政ロシアで絶大な権力を行使した「怪僧」ラスプーチンが暗殺される。
- 1917年2月:ロシア革命でロマノフ王朝は崩壊。
- 1917年7月16日:ペテログラードで武装デモ(七月蜂起)。
- 1917年7月18日:七月蜂起が鎮圧され、レーニンがフィンランドへ逃亡。ボルシェヴィキが非合法化される。
- 1917年7月19日:ロシア臨時政府がレーニンの逮捕を命じる。
- 1917年10月:ウラジーミル・レーニンはポーランド・バルト三国・フィンランドの独立承認で帝国の西方領土の一部を手放した後、ボリシェヴィキ(共産党)を率いて内戦に勝利し、ソビエト政権を樹立。
- 1917年10月25日:ロシアの首都ペトログラードでボリシェビキが武装蜂起。翌朝までに首都の全ての拠点を無血占領(新暦11月6日十月革命)。
- 1917年11月7日:レーニン首班のソビエト政権が樹立(世界最初の社会主義国家が成立:11月革命)。
- 1917年11月8日:全ロシア・ソビエト会議が、無併合・無賠償の和平、土地私有権廃止などの「平和・土地に関する布告」を採択。
- 1918年7月3日:ロシア反革命派ホルバートが仮政府組織を宣言し、日本に援助を要請。
- 1918年7月17日:ロシア革命でニコライ2世が処刑される。
- 1920年1月13日:ラトビアがソ連より独立。
- 1922年12月30日:第1回全連邦ソビエト大会で、ソビエト社会主義共和国連邦の樹立宣言。
- 1925年1月15日:トロツキーがスターリン派との抗争で最高人民委員を解任。
- 1925年12月18日:ソ連共産党第14回大会で、スターリンの「一国社会主義」が採択される。
- 1926年10月23日:ソ連共和党中央委員会がトロツキーを政治局から追放。
- 1927年10月14日:ソ連が田中都吉駐ソ大使に日ソ不侵略条約の締結を提案。
- 1927年12月2日:全ソ連邦共産党大会でトロツキーらが除名に。
- 1928年1月4日:「土地所有禁止法案」を発表。集団農場「コルホーズ」の発足。
- 1929年6月28日:全農産物の強制取り立てを実施。
- 1932年8月7日:穀物を1個取っても10年の労働収容所送りとの「8月7日の法律」が可決される。
- 1932年11月9日:ソ連が日・満・ソ不可侵条約締結を提議(12月13日に日本は拒絶)。
- 1932年11月29日:仏・ソ不可侵条約が調印される。
- 1933年11月17日:アメリカがソ連を承認。
- 1934年12月1日:ソ連でスターリン大粛清が始る。
- 1936年12月5日:スターリンが「一国社会主義」体制の憲法(スターリン憲法)を制定。
- 1937年6月29日:日・ソ両軍がアムール川で衝突。
- 1938年7月29日:沙草峰で日・ソ軍が衝突(7月11日〜:張鼓峰事件)。
- 1938年7月30日:ソ連と満洲の国境で、ソ連軍と日本軍守備隊が国境紛争。8月10日に停戦協定(張鼓峯事件)。
- 1938年7月31日:日本軍がソ連軍を夜襲(7月11日〜:張鼓峰事件)。
- 1938年8月6日:ソ連軍機械化部隊が日本軍に大反撃(7月11日〜:張鼓峰事件)。
- 1938年8月10日:張鼓峰でのソ連との国境紛争で日本軍が敗北。
- 1938年10月12日:日ソ停戦協定が成立(7月11日〜:張鼓峰事件)。
- 1938年11月26日:ソ連がポーランド不可侵条約を更新。
- 1939年6月27日:ソ満国境ボイル湖上で日・ソが空中戦に突入。
- 1939年7月1日:日本軍がノモンハンで攻撃を開始(3日に敗退)。
- 1939年7月23日:ソ蒙軍大部隊がノモンハンで日本軍に逆襲し、空・陸で大激戦となる。
- 1939年9月17日:ソ連軍がポーランド東部に侵攻。ポーランド軍がドイツ軍に包囲され殲滅される。
- 1939年10月10日:ソ連がリトアニアを併合。
- 1939年11月30日:第2次大戦で、ソ連軍がフィンランドへ進撃。
- 1939年12月14日:国際連盟がソ連を除名。
- 1940年8月21日:ロシアの革命家・トロツキーが、亡命先のメキシコで暗殺される。
- 1940年12月18日:ヒトラーが対ソ作戦「バルバロッサ計画」の作戦案を指令。
- 1941年6月22日:第2次大戦でドイツ・イタリア・ルーマニアがソ連に宣戦。ドイツがソ連に侵攻開始(バルバロッサ作戦)。
- 1941年7月21日:第2次大戦で、ドイツ軍がモスクワを空襲。
- 1941年10月2日:第2次大戦で、ドイツ軍がモスクワへの総攻撃を開始。
- 1941年10月16日:第2次大戦で、ドイツ軍がソ連のオデッサを占領。
- 1941年12月1日:ソ連が日・ソ中立条約遵守を日本に通告。
- 1943年7月5日:第2次大戦で、ドイツ軍がソ連のクルスク周辺に大量の戦車師団を投入(12日に敗退:クルスクの戦い)。
- 1943年12月3日:米・英・ソによる「テヘラン宣言」発表。対独第2戦線結成を決定。
- 1944年9月4日:ソ連軍がハンガリーに進出。
- 1944年12月29日:ソ連軍がハンガリーの首都ブタペストを攻略(バルジの戦いでヒトラーは最後の賭けに敗れる)。
- 1945年1月12日:ソ連軍がドイツ戦線を突破しポーランドに進撃。
- 1945年6月28日:ソ連軍司令部が満州侵攻作戦の準備を指令。
- 1945年8月8日:ソ連が日本に対し宣戦を布告(通告の数十分後一斉に進撃開始、ソ連国境を越え北満州・朝鮮・樺太に攻め込む)。
- 1945年8月9日:ソ連軍が満洲・朝鮮・樺太の国境を突破。
- 1945年8月20日:ソ連のスターリン書記長が日本人捕虜の労働使役を指令。
- 1945年8月20日:樺太の真岡で、上陸したソ連軍と日本軍が戦闘開始。
- 1945年7月17日:ドイツ・ベルリン郊外のポツダムで、トルーマン・米大統領、チャーチル・イギリス首相、スターリン・ソ連首相が集まり連合国首脳会議(ポツダム会談)を開く(26日に米・英・中が軍国主義の永久追放などを盛り込んだ対日ポツダム宣言を発表)。
- 1945年10月24日:国連加盟。
- 1945年12月16日:アメリカ・イギリス・ソ連の3か国が、モスクワ外相会議を開会(極東委員会・対日理事会・米ソ合同委員会の設置、朝鮮臨時政府樹立、5年間の信託統治など朝鮮処理案で合意)。
- 1946年:旧ドイツ領の東プロイセンの北部をカリーニングラード州、日本に侵攻して占領したサハリン島南部(南樺太)とクリル列島(千島列島、歯舞諸島・色丹島を含む)全域をサハリン州として編入。
- 1948年6月24日:ソ連が西ベルリンへの道路を遮断し、食糧輸送を禁止。西側は空輸作戦を開始。
- 1949年8月29日:カザフスタン砂漠で原爆の実験に成功。。
- 1949年9月28日:ユーゴスラビアとの友好援助条約を破棄。
- 1950年1月12日:ソ連が、スパイ・反逆などの罪に対し死刑復活。
- 1953年8月8日:ソ連が水爆保有を声明。
- 1953年8月20日:ソ連が水爆実験の成功を発表。
- 1953年9月12日:ソ連共産党第一書記にフルシチョフが就任。
- 1954年:黒海沿岸のクリミア半島(クリミア州)がウクライナに割譲され、現在のロシア連邦にあたる領域となる。
- 1954年6月27日:世界初の工業用原子力発電所がソ連で運転開始。
- 1956年11月1日:ソ連軍が反ソ暴動中のハンガリーに侵入。
- 1956年11月4日:ハンガリー騒乱でソ連軍がブダペストを制圧。親ソ派のカダル政権が成立。
- 1957年8月22日:大陸間弾道弾(ICBM)の発射実験に成功。
- 1957年8月26日:大陸間弾道弾(ICBM)の実験に成功。
- 1957年10月4日:世界初の人工衛星の打ち上げにソ連が成功。
- 1957年11月3日:ソ連が「ライカ」を乗せた人工衛星「スプートニク2号」打上げ。史上初の生物打上げ実験に成功。ライカはシベリアンハスキーの雑種で、性別はメス。打ち上げの6時間後には死んでいたとされる。
- 1957年12月6日:日ソ通商条約調印。
- 1959年1月2日:世界初の月ロケット「ルーニク1号」の打上げに成功。軌道が逸れて太陽を周回する人工惑星「メチタ」となる。
- 1959年9月14日:ソ連の宇宙探査機「ルーニク(ルナ)2号」が月面の「晴の海」に衝突。月に到着した初の人工物体。
- 1959年10月4日:ソ連が無人宇宙ステーション「ルナ3号」の打ち上げに成功。
- 1959年10月7日:ソ連の月探査機「ルナ3号」が初めて月の裏側の撮影に成功。
- 1959年10月26日:ソ連の無人宇宙ステーション「ルナ3号」が初めて月の裏側の写真撮影に成功(月は自転周期と公転周期が同じなため、人類はそれまで月の裏側を見たことがなかった)。
- 1961年8月30日:核実験再開を発表。
- 1961年10月30日:ソ連共産党大会でモスクワ・赤の広場からのスターリンの遺体撤去を決議。
- 1961年10月30日:ソ連が50メガトン核爆弾実験を実施。
- 1962年9月1日:「ソ連・キューバ軍事経済相互援助協定」の調印。
- 1962年10月28日:ソ連がキューバから攻撃的兵器を撤去するよう指令。
- 1963年7月5日:中国のトウ小平総書記とソ連のフルシチョフ首相が会談。イデオロギー論争で対立し、20日に会談決裂。
- 1964年10月15日:フルシチョフソ連首相兼第一書記が辞任。後任としてコスイギンが首相、ブレジネフが第一書記に就任しトロイカ体制に。
- 1967年10月18日:ソ連の金星探査機「ベネラ(金星)4号」の観測カプセルが初めて金星の大気を観測。
- 1968年8月20日:ソ連・東欧軍が、「チェコ・スロバキア」に侵入し、民主化運動「プラハの春」を圧殺。
- 1969年1月16日:ソ連の宇宙船ソユーズ4号と5号が初の有人宇宙船同士のドッキングに成功。
- 1969年11月24日:アメリカとソ連が核不拡散防止条約に批准。
- 1971年6月30日:ソ連の3人乗り宇宙船「ソユーズ11号」が帰還途中で事故。乗員全員死亡。
- 1975年10月17日:ジスカールデスタンフランス大統領がソ連を訪問、「仏ソ友好協力宣言」を発表。
- 1975年7月17日:ソ連の「ソユーズ19号」とアメリカの「アポロ18号」が大西洋上空で初のドッキング成功。
- 1978年1月11日:ソ連の宇宙船「ソユーズ26号」と「ソユーズ27号」、軌道科学ステーション「サリュート6号」が、史上初の3つの宇宙船によるドッキング。
- 1978年11月3日:ソ連とベトナムが友好協力条約に調印。
- 1980年10月23日:ソ連のコスイギン首相が辞任。
- 1980年代:ソ連の指導者となったミハイル・ゴルバチョフは冷戦を終結させる一方、ペレストロイカ、グラスノスチを掲げてソ連を延命させるため改革に取り組むが、かえって各地で民族主義が噴出、共産党内の対立が激化。
- 1980年7月19日:第22回オリンピック・モスクワ大会が開催される(〜8月3日:1979年12月のソビエト軍・アフガン侵攻に対する制裁措置としてアメリカのカーター大統領がモスクワオリンピックのボイコットを表明、日本を含む西側諸国が不参加の中、全203種目中でソビエトが80個、東ドイツが47個の大量の金メダルを獲得)。
- 1982年6月29日:米ソ主脳が戦略兵器削減交渉(START)を開始。
- 1982年11月10日:ソ連のブレジネフ書記長が死去。12日にアンドロポフ政治局員を後任に選出。
- 1983年8月18日:アンドロポフ書記長が、衛星攻撃兵器の配備凍結を宣言。
- 1983年11月23日:ソ連がアメリカにINF制限交渉の無期限中断を通告。
- 1984年10月13日:ソ連が巡航ミサイルの実戦配備を発表。
- 1985年7月29日:ゴルバチョフ書記長が、8月6日からの核実験の停止を発表。
- 1985年9月27日:ルイシコフが首相に就任。
- 1985年10月15日:ソ連共産党中央委員会総会で24年ぶりに党綱領を改定。
- 1986年12月19日:ソ連の反体制活動家で物理学者であるサハロフ夫妻の流刑が解除される。
- 1987年11月24日:アメリカ国務長官とソ連の外相がINF(中距離核戦力)全廃で完全合意。
- 1987年12月8日:レーガン・米大統領とゴルバチョフ・ソ連書記長が中・短距離核戦力(INF)全廃条約に調印(7年間にわたる交渉の末冷戦が終息)。
- 1988年7月13日:ソ連初の株式会社が誕生。
- 1988年8月26日:農業の自由化。個人による農地所有や土地賃貸・顧用を許可。
- 1988年12月7日:アルメニアでM7.0の大地震。死者5万人以上。
- 1988年12月7日:ゴルバチョフ書記長が国連でソ連軍兵力の50万人削減を表明。
- 1989年12月3日:ブッシュ米大統領とゴルバチョフソ連書記長がマルタで会談(東西冷戦終結を宣言)。
- 1990年1月16日:エリツィン人民代議員が北方領土問題で「時間をかけて5段階で」との見解を表明。
- 1990年6月12日:ボリス・エリツィンはロシア共和国と改称して主権宣言を行い、自らを大統領とした。
- 1990年7月12日:ボリス・エリツィン、ソ連共産党からの離党を宣言。
- 1990年9月30日:韓国とソ連の外相が国連本部で即日国交樹立の共同コミュニケに調印。
- 1990年10月15日:ゴルバチョフ大統領のノーベル平和賞受賞が決定。
- 1990年12月14日:廬泰愚・韓国大統領とゴルバチョフ・ソ連大統領が「朝鮮半島冷戦終結への共同努力宣言」に調印。
- 1991年7月10日:エリツィンがロシア共和国大統領に就任。
- 1991年7月31日:アメリカとソ連、第1次戦略兵器削減条約(START I)に調印(冷戦の実質的終結)。
- 1991年8月19日:ソ連のヤナーエフ副大統領ら保守派がゴルバチョフ大統領を休養先で軟禁(8月クーデター)。
- 1991年8月21日:ソ連の副大統領らによるクーデターが市民の抵抗により失敗。首謀者がモスクワを脱出。
- 1991年9月6日:レニングラードがサンクトペテルブルグに改称。
- 1991年10月11日:ソ連崩潰により秘密警察(KGB)が解体、74年の歴史に幕。
- 1991年12月17日:ゴルバチョフ・ソ連大統領とエリツィン・ロシア大統領がソ連邦の年内消滅で合意。
- 1991年12月21日:アルマアタで旧ソ連11共和国の首脳による会議が開かれ、ソ連邦の消滅を決議。ソ連の歴史に幕(アルマアタ宣言)。
- 1991年12月25日:ロシア革命以来74年間続いたソビエト社会主義共和国連邦がゴルバチョフ辞任により消滅。
- 1991年12月26日:ソ連の最高会議・共和国会議でソ連の消滅を宣言。
- 1992年5月:ロシア連邦条約により、現在のロシア連邦(ロシア)の国名が最終確定。
- 1993年10月17日:ロシアが日本海に核廃棄物を投棄。
- 1994年12月31日:ロシア軍がチェチェン共和国の首都グロズヌイに突入し総攻撃を開始。
- 1996年7月3日:大統領決選投票でエリツィン大統領が再選。
- 1996年11月16日:ロシア火星無人探査機マルス96が地球周回軌道の脱出に失敗し落下。
- 1991年1月13日:リトアニアにソ連が軍事介入(血の日曜日事件)。
- 1998年8月17日:ロシア政府のロシア・ルーブル実質切下げと債務償還の一時停止により、ロシア財政危機が始まる。
- 1999年12月8日:当時のエリツィン大統領と、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領との間で、将来の両国の政治・経済・軍事などの各分野での統合を目指すロシア・ベラルーシ連邦国家創設条約が調印される。
- 1999年12月31日:エリツィン大統領が辞任。代行にプーチン首相を指名。
- 2000年8月14日:ロシア原子力潜水艦事故発生。乗組員118人は全員死亡。
- 2002年10月23日:モスクワで劇場占拠事件発生、特殊部隊の強行突入で一般人129人も死亡。
- 2004年9月1日:北オセチア共和国でベスラン学校占拠事件起こる(〜3日)。人質となった学校の生徒やその親、教員ら1000人以上が死傷。
- 2006年7月15日:ロシアが初めて議長国となったサミットが、サンクトペテルブルクで開幕。
ロシアの文化
- 「ロシア」の国名は、現在のロシア北西部とウクライナ、ベラルーシにあたるルーシという地域をギリシア語の発音によって変更された名前。この名は16世紀のイワン4世(雷帝)の頃に使われ始め、18世紀初頭のピョートル1世(大帝)が称したことにより正式の国名となった。
- 日本とは海を隔てた隣国で、日本との間には国境が不確定な部分があるが、北方領土他を除く日本の最北端である北海道稚内市の宗谷岬とサハリン州のサハリン島(樺太島)南端の距離は43kmであり、日本の領土からみて最も近くにある国(ただし、サハリンの南半分については、日本政府は「国際法上は所属未定地」との立場を取っている)。 また、実効支配という観点から見ると、北海道根室市の納沙布岬と、日本が領有権を主張しているがロシアが実効支配している、いわゆる北方領土の貝殻島との距離はわずか3.7kmしかない。
- 首都モスクワは、「沼地【mosk】」+「水【va】」が語源で「沼地の川」との意味。元々は川の名前であったモスクワが、河畔の集落の名前となったといわれている。
- 国旗はソビエト時代に社会主義の象徴とされた「赤い旗」を降ろし、上から白・青・赤の三色旗を掲げた。これは新しくデザインされたものではなく、帝政ロシア時代に使われていた旗を復活させたもの。白は高貴と率直を、青は忠義と誠実を、赤は愛と勇気をそれぞれ表している。また、白は白ロシア人(ベラルーシ人)、青は小ロシア人(ウクライナ人)、赤は大ロシア人(ロシア人)との意味も込められている。
- リトアニアの南、ポーランドの北にはカリーニングラード州との飛び地がある。13世紀頃にこの土地はケーニヒスベルグと呼ばれるドイツの領土であったが、第2次大戦でドイツが敗れたため戦勝国であったソ連の統治下に入った。
- 「クレムリン」と言えば、現在ではモスクワにある宮殿を指すことが多いが、本来はロシア語の「城塞」を意味する普通名詞であり、ノヴゴロドやカザン、アストラハンにもクレムリンはあった。それらの多くは河川に面した高台に建設され、木や石、レンガなどの壁で囲まれた内部が領主や高僧の住居となっていた。
- 国際連合安全保障理事会常任理事国の1つ。
- 上海協力機構加盟国。
- 独立国家共同体加盟国。
- アジア太平洋経済協力会議(APEC)加盟国。
当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
地理、
国、
ロシアとリンクを辿ると、当ページ
ロシアに辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/country/rossiya/rus.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年03月05日 最終更新:2007年10月02日