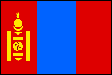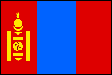モンゴル
モンゴルの基本情報
- 最終更新
- 2007-04-20T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/e_asia/mng.html#basic
- 国・地域名(ISO 3166-1による英語名)
- モンゴル国【Mongolia】。
- 首都
- ウランバートル【Ulaanbaatar】
- 国旗
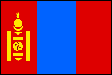
- 人種
- モンゴル人(全体の95%)及びカザフ人等
- 言語
- モンゴル語(公用語)
- 宗教
- チベット仏教等(チベット仏教は1921年の革命後勢力衰退していたが民主化(1990年)以降に復活。1992年2月の新憲法は信教の自由を保障。)
- 通貨
- トグログ:Tugrik(MNT)
- 3文字国名コード/2文字国名コード/数字国名コード
- MNG/MN/496
- 人口/面積
- 2,751,314人/1,565,000平方キロメートル(日本の約4倍)
- 国歌/国花/国鳥
- モンゴル国歌/-/オジロワシ(タカ科)
- 漢字による表記
- 蒙古/莫臥児
- 時間帯
- UTC (+7 ~ 8)(DST: (+8 ~ 9))
- ccTLD
- .MN
- 国際電話番号
- 976
モンゴルのその他情報
- 最終更新
- 2007-04-20T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/e_asia/mng.html#other
モンゴルの地形
東アジアの中心に位置し、南は中国、北はロシアと国境を接する内陸国。平均高度1580mの高原状地形で、北西部は河川と湖の多い山岳地、北東には針葉樹林が広がり、南部はゴビ砂漠、中央部から東部は草原となっている。西には標高4,300mのアルタイ山脈と標高3,500mのハンガイ山脈がそびえる。塩湖に終る内陸河川もみられ、重要な河川はバイカル湖に注ぐセレンゲ川と太平洋にそそぐヘルレン川。ステップ草原と砂漠が国土の80%を占めている。
モンゴルの気候
典型的な大陸性気候で、年間を通じて乾燥し、降雨は夏季にわずかにあるのみ。年間降水量は首都ウランバートルで200mm程度。気温は日較差・年較差ともに大きく、7〜8月の日中はかなりの高温になるが、冬季の半年間は平均気温が零下となり、-35℃まで下がる。
モンゴルの経済
古来より牧畜が結唯一の生活手段で、以前は遊牧中心であったが定着放牧化が進んでいる。現在では農牧業従事者は就労者数の半分以下。集団農場は民営化された。ヒツジ、ヤギ、牛、馬、ラクダが飼育され、羊毛と畜産品は重要な輸出品である。セレンゲ川流域では麦や綿花の栽培がおこなわれている。地下資源ではモリブデンが豊富で、ほかに銅、石炭も産出される。
主要貿易品目
輸出は鉱物資源(銅精鉱、モリブデン精鉱、蛍石)、牧畜産品(皮革、羊毛、カシミア)。輸入は石油製品、自動車、機械設備類、日用雑貨、医薬品。
主要貿易相手国
輸出は中国、カナダ、アメリカ、ロシア、イギリス。輸入はロシア、中国、日本、韓国、カザフスタン。
モンゴルの歴史
- 20世紀初頭:清朝は北方の自国領の人口密度を高くすることでロシア側の侵略を防ぐ政策を実施。それまでの辺境への漢人入植制限を廃止。内モンゴルでは遊牧地が漢人により耕地に変えられ、モンゴル民族のうちに反漢・独立感情が高まり、反漢暴動が頻発。
- 1911年:辛亥革命が起こると、ロシアに独立のための財政援助を求めていたハルハ地方(外モンゴルの多くの地域)の王侯たちは清からの独立を宣言。
- 1913年:チベットとの間で相互承認条約を締結。
- 1915年:キャフタ条約で中国の宗主権下での外モンゴル「自治」のみが、清の後を引き継いだ中華民国とロシアによって承認されるが、内モンゴルについてはこの地への進出をうかがっていた日本に配慮して現状維持とされる。
- 1919年 自治を撤廃し中国軍閥の支配下に入る
- 1920年10月:赤軍との内戦で不利な状況に追い込まれていたウンゲルン率いる白軍が体制の建て直しのためにモンゴルへと侵入して中国軍を駆逐、ボグド・ハーン政権を復興させる。
- 1921年7月11日:活仏(カツブツ)を元首とする君主制人民政府成立(モンゴル革命)。
- 1924年11月26日:活仏の死去に伴い人民共和国を宣言。モンゴル人民共和国(社会主義国)が成立。
- 1936年6月28日:「蒙古自治運動」の徳王が日本(関東)軍の援助によって内蒙古軍政府を結成。
- 1945年8月10日:モンゴルが対日宣戦を布告。
- 1961年10月27日:国連加盟。
- 1990年3月:複数政党制を採用。
- 1990年9月:大統領制に移行、初代大統領にP.オチルバトを選出。
- 1992年2月12日:モンゴル国憲法施行(1月13日採択)、国名変更(モンゴル人民共和国→モンゴル国)。
- 1992年6月28日:第1回総選挙(与党人民革命党の圧勝)。
- 1996年6月30日:第2回総選挙(野党民主連合の大勝)。
- 2000年7月2日:第3回総選挙(野党人民革命党の圧勝)。
- 2004年6月27日:第4回総選挙(野党祖国・民主連合の躍進)。
モンゴルの文化
- モンゴル語名「モンゴル・オルス」のモンゴルは民族名で、オルス〜ウルスは「国」を意味する。モンゴルの民族名の語源は明らかではないが、モンゴル民族のアイデンティティーの基礎が出来上がったのはチンギス・ハーンのモンゴル帝国時代と考えられる。
- モンゴル民族の居住地域であるモンゴル高原のうち、清国支配下において中国語で外蒙古とよばれたゴビ砂漠以北の一帯にほぼ該当する領域を国土とする。これに対し、南部の一帯がかつての内蒙古で、現在は中国領となっており、「蒙古族」(中国国籍のモンゴル人)のための「民族区域自治」単位として内モンゴル自治区等が置かれている。
- モンゴル人の主な宗教はチベット仏教で、歴史的にチベットとの関わりが深い。またシャーマニズム信仰も根深い。どちらも社会主義時代は抑圧されていたが、民主化以降復活を遂げている。
- 多くの国民は、人種的には日本人と同じモンゴロイドで、いくつかの遺伝形質の傾向が一致し、モンゴル語と日本語が文法的に比較的似通っていることから、日本人のルーツに近いという説もある。旧石器時代の氷河期に当時陸で繋がっていた間宮海峡や宗谷海峡を通ってモンゴル人の祖先が日本列島にも入ってきたという説も有力である。
- モンゴルでは、フブスグルなど一部の地域をのぞき、魚を食べる習慣がなかった。
- 西部のバヤンウルギー県はカザフ人(イスラム教徒)が人口の大半を占め、学校教育もカザフ語とモンゴル語で行われる。モンゴル国憲法は、モンゴル語を唯一の公用語と定めており、本来はバヤンウルギー県においても、行政・議会など公的な場面でのカザフ語の使用は認められていない。しかし、公文書はモンゴル語で作成されるものの、実際には同県の少数者であるモンゴル人の多くもカザフ語を話し、カザフ語が議会を含むあらゆる場面での共通語となっている。
- 上海協力機構オブザーバ加盟国。
当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
地理、
国、
東アジアとリンクを辿ると、当ページ
モンゴルに辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/country/e_asia/mng.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年03月05日 最終更新:2007年04月20日