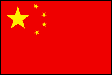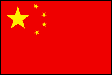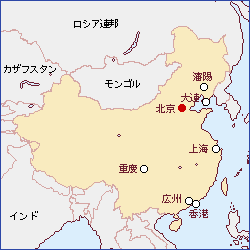���ؐl�����a��
���ؐl�����a���̊�{���
- �ŏI�X�V
- 2007-04-02T00:00:00+09:00
- ���̋L����URI�Q��
https://www.7key.jp/data/country/e_asia/chn.html#basic
- ���E�n�於�iISO 3166-1�ɂ��p�ꖼ�j
- ���ؐl�����a���yChina�z�B�����̉p��\�L�́APeople's Republic of China�B
- ��s
- �k���i�y�L���j�yBeijing�z
- ����
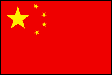
- �l��
- �������i���l����92%�j�A�`�������i1,600���l�j�A�����i1,000���l�j�A�i900���l�j�A�~���I���i800���l�j�A�E�C�O�����i700���l�j�A�C���i700���l�j�A�����S�����i500���l�j�A�`�x�b�g���i500���l�j�A�u�[�C�[���i300���l�j�A���N���i200���l�j�Ȃ�55�̏�������
- ����
- ����i������j�i���p��j
- �@��
- �����E�C�X�������E�L���X�g���Ȃ�
- �ʉ�
- �l�����FYuan�iCNY�j
- 3���������R�[�h/2���������R�[�h/���������R�[�h
- CHN/CN/156
- �l��/�ʐ�
- 3,742,482�l/9,596,960�����L�����[�g���i���{�̖�25�{�j
- ����/����/����
- �`�E�R�i�s��/�{�^��/�L�N/-
- �����ɂ��\�L
- ����
- ���ԑ�
- UTC +8�iDST: �Ȃ��j
- ccTLD
- .CN
- ���ۓd�b�ԍ�
- 86
���ؐl�����a���̂��̑����
- �ŏI�X�V
- 2007-04-02T00:00:00+09:00
- ���̋L����URI�Q��
https://www.7key.jp/data/country/e_asia/chn.html#other
���ؐl�����a���̒n�`
���A�W�A�̃��[���V�A�嗤���݂Ɉʒu���A���̍��y�̑嗤���́u�����嗤�v�Ƃ��Ă��B���V�A�A�����S���A�J�U�t�X�^���A�L���M�X�A�^�W�L�X�^���A�A�t�K�j�X�^���A�p�L�X�^���A�C���h�A�l�p�[���A�u�[�^���A�~�����}�[�A���I�X�A�x�g�i���A�k���N�ƍ�����ڂ��A�܂����V�i�C����������{���؍��Ƃ��ڂ��Ă���B�������݂̕����n�т��琼�i�ނɂ�Ď���ɂɕW���������Ȃ�B�����͗g�q�]�≩�͗���ɍL��ȉ��ϕ��삪�L����A�����̓p�~�[�������A���ĎR���A�V�R�R���A�`�x�b�g�����Ȃǂ̎R�x�ƍ������A�Ȃ�A���̊ԂɃ^�����A�l��Ȃǂ̍L��Ȗ~�n���W�J���Ă���B��ȍ����̓S�r�����A�^�N��=�}�J�������B��Ȑ�͉��́A���]�i�g�q�]�j�A�����]�A���R����B
���ؐl�����a���̋C��
�S�̓I�ɂ͉��тɑ����A���������A�k���g�̋C��B�����͑嗤���C��ŁA�����S������^�����~�n�ɂ����ăX�e�b�v�ƍ������L����B�`�x�b�g�����Ȃǂ̎R�x�n�т͍��R�C��B���k�n���͓~�Ɋ���ȑ嗤����ю����C��ŁA���́A�g�q�]����̉ؒ��͉��у����X�[���C��B�ؓ�͈��M�у����X�[���C��B
���ؐl�����a���̌o��
�_�Ƃł͎s�ꌴ�����d���������Y�������������ꑝ�Y�ɐ����A�����˂Ƃ���x�_���o�����Ă���B�_�Y���A�o���������A�o���z��1�����邪�A����œ��H�̑����ɔ����������v�̑����͎����p������A�����鎖�Ԃ������Ă���B�����₤�悤�ɁA�O�m�A�����ʂ��܂ߋ��Ƃ��}�������Ă���B�H�Ƃł͏]���̌y�H�Ƃɉ����A�d���w�H�Ƃ�d�q�Y�Ƃ̐L�т��������B������ƂƂ���_���ɂ�鏬�K�͔_���H�ƂƊO���n��Ƃ��������Ă������A���c��Ƃ����c�����ꋣ���͂��l��������B���W���鉈�ݕ��Ƃ͑ΏƓI�ɓ������̑����͎��c����A�n�x�̊i���͎Љ��`�̗��O���������܂łɊg��B���Ă͍H�Ƃ̒��S�n�ł��������k��������I�ȍ��L��Ƃ������A���v�J���̔g�ɏ�ꂸ�A���]�f���^���]�f���^�̐�i�n��Ƃ̌o�ϊi���͊J������ł������B���̂��߁A�������{��2000�N�����琼����J���Ⓦ�k�U�����d�_����Ƃ��A�����㔭�n��̊J���ɏ��o���Ă���B�������A���C���Ɠ������Ƃ̊i���͉������ꂸ�A�ˑR�Ƃ��ē������������C���̕����o�ϐ������������A�i���͊g�債�Ă���B�܂��G�l���M�[���v�̋}���ɂ��Ζ��A���̑����́A���E�ɂ��傫�ȉe��������ڂ��Ă���B���݂̒����́A�u���E�̍H��v�ƌĂ��قǐ����Ƃ�����B���̌������ƂȂ����̂��A�����l����A�c��Ȑl����w�i�ɂ������ݏ�����v�č��O���̎��{�����ƁA�����l����v���̈����Ȑ��i�A�o�̊g��ł���B�������A���������̖��͂ł������l����̈����́A���p���Œ����ɐi�o�����Ƃ��J���͂����ߑ��������Ƃɂ����ɍ��w���̐l�ނ��s������悤�ɂȂ�A�܂�����ɔ��������������㏸���A�����̖ʂł͓���A�W�A���D�ʂɗ�������B��i�n����܂߂Ė������{�����W���Ă��Ȃ����ƁA�����̕��s�A�Љ�ɍL�����݂���@�̌y���A�s�Ǎ��̒~�ρA�n�x�̍��̊g��A�U�u�����h���i�E��@�R�s�[�i�̐����E�̔��������ȂǂƂ������������݂���B
��v�f�Օi��
�A�o�͋@�B�d�C���i�A�n�C�e�N���i�A�@�ہE�����i�B�A���͋@�B�d�C���i�A�n�C�e�N���i�A�W�ω�H�E�}�C�N���g�����i�B
��v�f�Ց��荑
�A�o���A�����J�AEU�����A���`�A���{�B�A���͓��{�AEU�����A�؍��AASEAN�����B
���ؐl�����a���̗��j
- �I���O2070�`�I���O1600�N���F��
- �I���O1600�`�I���O1023�N���F�u
- �I���O1023�`�I���O256�N�F�����u��|���A���������B���u�̔N��ɂ��Ă͕������Y�̌����ɂ�錋�ʂ��ł����m�ƍl������B
- �I���O770�`�I���O403�N�F�t�H����B���̓��J�Ǝ����������Ċ����g�p�̒m�������J���x�����W���͂��߂Ƃ��鏔��ɕ��y���A����̗��j���`������悤�ɂȂ�B����������ďt�H����ɓ���Ƃ���B
- �I���O403�`�I���O221�N�F�W���E��E鰂ɕ��A�퍑����˓��B
- �I���O221�`�I���O207�N�F�`�̎���B�`���E����6����łڂ����ؓ���B
- �I���O206�`8�N�F�O���B�`�ŖS��A�^�̍��H�Ƃ̑^���푈�ɏ����A���M�������B
- 8�`23�N�F�V�̎���B�O�ʂ̉��͂��O���c�邩���ʂ�ӒD�������B
- 25�`220�N�F�㊿�B�O���̌i��̎q���̗��G�i������j�����͌R��j��A�����ċ��B
- 220�`280�N�F鰁A冁A���̎O������B�����̎q���������邩��T�������ʂ���ƁA冂̗��������c��𖼏�葦�ʁA����Ɍ��̑��������Ƃ��đ��ʂ��A�O������ɓ���B
- 265�`316�N�F���W�B�W���i�n����鰂̌�����T�������ʂ������B�����A�ٖ����܌ӂ̐N���ɂ�萊�ށB�ٖ����̊��ɖłڂ����B
- 317�`420�N�F���W�B�c���ł�����l�����c��������E�i�n�͍͂]��ɓ���A���N�ő��ʁi����j�B����𒆌��̐W�Ƌ�ʂ��ē��W�Ƃ����B
- 304�`439�N�F�܌ӏ\�Z������B
- 439�`589�N�F��k������B
- 581�`619�N�F�@
- 618�`907�N�F��
- �ܑ�\������
- 960�`1127�N�F�k�v
- 1127�`1279�N�F��v
- 1271�`1368�N�F��
- 1368�`1644�N�F��
- 1616�`1912�N�F��
- 1689�N9��7���F���V�A�ƍ������ׂ̈́u�l���`���X�N���v�ɒ���B
- 1839�N9��28���F�C�M���X�Ƃ̊Ԃň��А푈���u���i�`1842�N�j�B
- 1856�N10��6���F�����l���L�ŃC�M���X�l���D���̏����D�E�A���[�����A�L�B�`�O�Ő��������ɂ��Ռ��B�C�M���X���C�M���X�����J�Ǝ咣�������Ɂi�A���[�������j�B
- 1842�N8��14���F���А푈�Ő������C�M���X�ɍ~���B
- 1850�N12��10���F�����ŁA�閧���ЁE����̍^�G�S�������V���̗����N�����B
- 1851�N1��11���F���c���ɂ����Ĕq����͍������V���Ƃ��A���g��V���Ə̂���i�����V���̗��j�B
- 1871�N7��4���F���V�A�������A�W�A�̐����́E�C���n���ɏo������́i�C�������j�B
- 1871�N7��29���F�����C�D���K�������i���{���S���͈ɒB�@��A�����ԍŏ��̏��j�B
- 1884�N6��23���F�x�g�i���̏@�匠���߂��镧���푈���u���B
- 1894�N7��25���F���{�R�Ɛ����R������E��R�̊ԂőΛ����A�L�����œ��{�͑��������͑����U���B
- 1894�N8��1���F���{�������ɐ��z���B�����푈���J��B
- 1896�N7��21���F�����ʏ��q�C������B
- 1898�N8��6���F�����Ő����@���A�錠�Ɨ����N�吧�ւ̓]����}��������H�i����̐��ρj�B
- 1900�N6��21���F�`�a�c�����Ő��������ĉp�ƕ��ɚҘI��8�����ɐ��z���B
- 1900�N12��30���F���g�c����u�`�a�c�����v�i�`�a�c�̗��j�ɂ��ėv������Ă���12�ӏ��̍u�a�����𐴍�������B
- 1902�N7��14���F�k�����݂�5�����g�i���E�p�E���E�ƁE�Ɂj���A�k�����ςŐڎ������V�Ís���ҕt�����𐴍��O�����ɑ��t�i18���A�����͏������j�B
- 1905�N12��22���F���B�Ɋւ��郍�V�A�̗������p���̓���������i1906�N1��31����y�E���z�j�B
- 1908�N12��2���F������3�̟�V���铝��Ƃ��Ėk���ő��ʁB3�N��ɐh��v���őވʁB
- 1909�N8��6���F�����œ��݃{�C�R�b�g���n�܂�B
- 1911�N10��10���F�����Őh��v�����n�܂�i12��29�����������ؖ����Վ��哝�̂ɏA�C�j�B
- 1911�N12��17���F���{�ƃC�M���X�������A������k�a�������E�v���h�ɐ\�������B
- 1911�N12��18���F���������E�v���h�̓�k�a����c����C�ŊJ�ÁB
- 1911�N12��25���F�������S����̃C�M���X����A���B
- 1911�N12��29���F�h��v���ɂ���đ��������ؖ����Վ��哝�̂ɏA�C�B
- 1912�N�F���ؖ����������i����ɐ����͏��Łj�B
- 1913�N7��2���F�]���Ȃŗ��������͐��M��������̓Ɨ���錾�B�Ȍ�A���J�ȁA�Γ�ȁA�L���ȁA�����ȁA�l��Ȃ��Ɨ���錾�i�������v���J�n�j�B
- 1913�N8��5���F�͐��M�R���R���Ȃœ��{���Z�ċ֎������N�����B
- 1913�N8��11���F�����E�������͐��M�R�����{�l���Z���S�ցi���������j�B
- 1913�N9��11���F�������t�œ��{���ƒ��������ՓˁB
- 1914�N7��8���F�����������Œ��؊v���}�������B
- 1915�N12��23���F�_��s�E���pꟂ炪�����Łu�鐭���E�_��Ɨ��v��錾���썑�R��n�݁B������3�v���̎n��B
- 1916�N�F�͐��M���c��ɏA�C���鐭�ֈڍs�B�e�n�Ŕ������������B
- 1916�N9��1���F�ь������������g���A�A�ƓԎ����̉��������Ƃ��ē얞�B�E�������Âł̓��{�x�@���̒��݁E���n�����������ւ̓��{�R���ږ�̗b�قȂǂ�v���B
- 1917�N8��14���F��1�����ŁA�����k�����{���h�C�c�E�I�[�X�g���A�ɐ��z���B
- 1918�N7��28���F�����E���B���ɐԌR������A���{�R�������g�����J�n�i30���ԌR�͖��B�����́j�B
- 1918�N12��2���F���E�p�E�āE���E�ɂ�5�����������̓�k�����{�ɘa������������B
- 1919�N7��19���F�x�߁E���k�̊���q�œ��E�����R���Փˁi����q�����j�B
- 1920�N7��14���F���{�x���̈��J�h�i�i�Q���j�Ɖp�Č㉇�̒���h�i���Λt�j���퓬���J�n�i19�����J�h���s��i�Q�������E�F�����푈�j�B
- 1921�N7��1���F��C�Ŗё炪�������Y�}��1��S����\�ґ����J�ÁB�������Y�}�̐�����錾�B
- 1925�N6��23���F�����̍L�B�s����ŁA5�E30�����Ɏh�����ꂽ���p�f���B�C�M���X�������C���A�����̒����l�������i������j�B
- 1926�N7��9���F�Ӊ���A�����v���R���i�߂ɏA�C�i�k���̊J�n�j�B
- 1927�N8��1���F�]���ȓ쏹�Œ������Y�}���ŏ��̕����\���B�������Y�}�����߂Ċ��S�ɏ�������R�������i�쏹�\���j�B
- 1927�N9��1���F��V�œc���`����t�œ|�̔r���^�����N����B
- 1927�N10��16���F�����̖k���x�O�̎����X�Ŗk�����l�̍����{�̑�P�����B
- 1927�N12��11���F�������Y�}���L�B����I�N���L���\�r�G�g���{�i�L�B�R�~���[���j�������i�L���\���j�B
-
- 1928�N7��19���F�����������{�����ؒʏ����p����ʍ��B
- 1928�N7��21���F��C�őS���������J�Â����B
- 1928�N7��25���F�A�����J�������������{�����F�B
- 1928�N10��8���F�Ӊ�������������{��ȂɏA�C�B
- 1928�N12��20���F�C�M���X�������������{�����F���u�ŋ���v�ɒ���i�����̎���ŏ��F�j�B
- 1929�N12��2���F�����X�Ŗk�����l�̓��������B
- 1929�N12��17���F�������{�́A�����ыg���g���u�Ή�21����v���v�Ɋ֗^�����Ƃ��ăA�O���}�����ۂ�ʍ��i�����O���ւ̍U�����܂�j�B
- 1930�N7��27���F�g�R���������́B�����\�r�G�g���������B�������Y�}�̑O�g�B
- 1930�N7��28���F�����̓��{�̎��ق��������Y�R�ɏĂ����B
- 1930�N10��6���F�����̊ԓ����䑺�œ��{�x��2�l���������ɎˎE�����������������B
- 1930�N12��27���F�Ӊ�ΌR����1���|������J�n�B
- 1931�N6��27���F�����S�������̎Q�d�{�����E�����k���Y��т��A�������ɂ��E�Q�����i���F���ς̉����Ɂj�B
- 1931�N7��2���F���t�x�O����R�ŁA���c�J�����߂���x�߁E���N�̔_�����Փˁi4���A����E�m��E����ł��x�ߐl�ɑ���\���N����A����94�l�E�d��96�l�F����R�����j�B
- 1931�N7��2���F�Ӊ���u�S�����u�ɍ�����̏��v�Ŕr���^���̒��~�������B
- 1931�N7��18���F�e�n�Ŕr���݉^�����N����B
- 1931�N9��24���F��C�̊w���E�J���҂̔����X�g�������e�n�ɔg�y�B
- 1931�N10��10���F�L�B�Ŋw�����N�������R���f�����e�������B
- 1931�N11��7���F���\�r�G�g���a���Վ����{�i�������{�j�����������B
- 1932�N�F���B����ŁA���{�R�͖k��̊͒��炪�����h�ɏP��ꕉ���i���B�����j�B
- 1933�N�F���B���Ƃ̋��E�t�߂̎R�C�ւɂāA�������R�����͏Փˁi�R�C�֎����j�B
- 1934�N7��15���F�������{�E�g�R���R���挭���́u�k��R���錾�v�\�B
- 1934�N10��15���F�����}���{�R�ɔs�ꂽ�������Y�}���A�ؓ�̍����n��e���������ւ̒������J�n�B
- 1935�N1��13���F�ё��w�������m���B
- 1935�N8��1���F�������Y�}���A�����v���H���̐헪��]�����R���~����������i8�E1�錾�j�B
- 1935�N12��8���F����M�R���֓��i���{�j�R�̌㉟���Ń`���n���ȓ����̍U�����J�n�i31���܂ł�6�����́F�@�����ρj�B
- 1935�N12��9���F�k���̊w�����R���^���B
- 1935�N12��18���F�k���əb�@�����ψ�������i�ψ����͑v�N���j�B
- 1935�N12��25���F�������Y�}���������lj�c���A�L�͂ȍR�������������i���ӍR���j�̌����Ȃǂ����c�i12�����c�j�B
- 1936�N9��17���F�L���ȟ����Œ������O�����{�l�Z��j�B
- 1936�N11��12���F���ÌR���֓��i���{�j�R�̉������������V�������ɐi���i�V�������j�B
- 1936�N11��23���F�֓��i���{�j�R�������̓��ÌR����������`�R�ɑ�s���A�S��_���ח��i�����̍R���^�������F�V�������j�B�����������{���͔T���~���A�����7�̑���ߕ߁i�R�����_�̒e���j�B
- 1937�N1��9���F�����ŋ��Y�}�w���̍R���f���i15���l���Q�����A�R���R���s���̊J�n�����c�j�B
- 1937�N7��7���F�k���x�O��ḍa���t�߂ŁA���{�R�ƒ����E�����}�R���ՓˁB�x�ߎ��ς̔��[�iḍa�������j�B
- 1937�N7��8���F�������Y�}���Γ��S�ʍR����Ăт�����B
- 1937�N7��11���F�b�a���������n��틦�肪�����i���{���{�͉ؖk�h���𐺖��j�B
- 1937�N7��17���F���������}�̏Ӊ�ƒ������Y�}�̎���������k���R������ō��Ӂi�I�R��k�j�B
- 1937�N7��29���F�b�@��������������ŁB
- 1937�N7��29���F�b���h���������{�̎�s�E�ʏB�̒�����������A�������Ă������{�R�������S�ł������{�l�E���N�l������142�l���s�E�i�ʏB�����j�B
- 1937�N8��22���F�������k�̍g�R�������v���R�攪�H�R�ɉ��҂����B
- 1937�N9��22���F���������}���������Y�}�Ƃ̍�������錾�������\�i�����́u�����c����v�R�G�錾�v�\�A23���Ӊ�͒����̍��@�I�n�ʏ��F�̒k�b�\�A��2���������삪�����j�B
- 1937�N9��23���F�����}�Ƌ��Y�}�̑Γ����삪�����i��2����������j�B
- 1937�N11��5���F�g���E�g�}���������݃h�C�c��g���Ӊ�ɑΓ��a��������ʍ��i�g���E�g�}���a���H��j�B
- 1937�N11��20���F�����������{�̏Ӊ���싞����d�c�ւ̑J�s��錾�B
- 1937�N12��10���F���{�R���싞���U�����J�n�B
- 1937�N12��13���F���{�R���싞���́B�哌���푈�I����A��̎��ɒ����l�R����w���q��\�s�s�E�����Ƃ̂�����u�싞��s�E�v���s��ꂽ�Ƃ̃f�}������邫�������ƂȂ�B�������{�͕����֑ދp�B
- 1937�N12��14���F�����q��𒆐S�ɒ��ؖ����Վ����{���k���Ɏ��������i���{�R�k�x�ߕ��ʌR���w���j�B
- 1938�N10��12���F���{�R�������R�ւ̕⋋���[�g��f���߁A�ؓ�̃o�C�A�X�p�ɏ㗤�A�L���U�������J�n�B
- 1938�N12��20���F���������d�c��E�o���ăn�m�C�ɓ����B
- 1939�N1��1���F�������{�͟��������i�v�����B
- 1939�N12��30���F���{�������̟��������Ɠ��؋��c���ނ��쐬�B
- 1941�N6��23���F�������Y�}���A�����ƈɁE���t�@�V�X�g���ۓ������̌������Ăт�����B
- 1941�N12��9���F�����E�d�c�̒����������{���A���E�ƁE�ɂɐ��z���B��ؖ����Վ����{�����{�ɐ��z���B
- 1943�N1��11���F�C�M���X�ƃA�����J�������d�c���{�ƐV��������i�݉ؓ���������j�B
- 1943�N12��1���F�t�����N�����E���[�Y���F���g�đ哝�́A�E�B���X�g���E�`���[�`���p�A�Ӊ�Β��ؖ����������u�J�C���錾�v�\�B
- 1945�N10��10���F�����}�E���Y�}���h�ԂŒ��ɒ���i�o������j�B
- 1945�N10��24���F���A�����B
- 1946�N7��12���F�����}�Ƌ��Y�}���S�ʓ���J�n�B
- 1946�N11��4���F�����������{�ƃA�����J���u�F�D�ʏ����v�ɒ���B
- 1947�N7��7���F�������Y�}������A�����{�����Ɠy�n���v���{�\�i7.7�錾�j�B
- 1948�N12��16���F�������Y�}�R���k���i���݂̖k���j�ɖ�������B
- 1949�N�F���ؐl�����a���������A���N�܂łɑ�p����ѕ����Ȃ̈ꕔ���ׂ��������ؖ����̓������y�𐧈��B�Ȃ��A��p���A�����̓��גn��͍��Ȃ����ؖ����̓������B
- 1949�N9��21���F���s���u�k���v�Ɖ��́B
- 1949�N9��30���F�������Y�}���{���ё���ȂɑI�C�i�`1978�N�ё���j�B
- 1949�N10��1���F�ё����ؐl�����a���ƒ����l�����{�̐�����錾�B�V����L��Ő������T���J�ÁB
- 1949�N10��15���F�����������{����s���d�c�Ɉړ]�B
- 1949�N12��7���F�Ӊ�����ؖ����̎�s���p�̑�k�Ɉڂ��i�Վ���s��J�s�j�B
- 1949�N12��30���F�C���h�����������F�B
- 1950�N1��14���F�������k���̃A�����J���̎��ق�ڎ��B
- 1950�N11��27���F���N�푈�ō��A�R��38�x�����z���k��i�ѕV�����钆���l���`�E�R����������j�j�B
- 1950�N12��2���F���A�R�������E�l���`�E�R�ɉ����ꕽ���P�ށB
- 1954�N9��20���F��1���S���l����\�҉�c�Łu���ؐl�����a�����@�v���̑��B
- 1958�N8��23���F�����l������R�����ؖ����̎x�z���ɂ�����哇�ɖC���B��2����p�C����@���n��i���哇�C�������j�B
- 1959�N8��7���F�����E�C���h���R�������ŕ��͏ՓˁB
- 1959�N10��20���F�����ƃC���h�̐��������̃R���J�ŗ����̎�������ՓˁB
- 1959�N12��4���F�����������B���c��E��V�̎ߕ�������B
- 1960�N9��1���F�������L���[�o�������������B
- 1961�N7��11���F�u���ؐl�����a���E�k���N�F�D���͏��v����B
- 1962�N10��20���F�������C���h�̍����n�тŒ����R���S�ʍU�����J�n�B
- 1963�N7��5���F�����̃g�E���������L�ƃ\�A�̃t���V�`���t����k�B�C�f�I���M�[�_���őΗ����A20���ɉ�k����B
- 1964�N10��16���F�������^�N���}�J�������ŏ��̌��������ɐ����i���E5�Ԗڂ̊j�ۗL���Ɂj�B
- 1965�N8��13���F������v�����͂��܂�B
- 1968�N10��31���F�������Y�}�����ψ����ŗ�����S�Ă̐E������C�B
- 1972�N9��29���F���{�ƒ����Ƃ̊Ԃ̍��𐳏퉻���������i�������������j�̒����k���ōs���A�c���p�h�Ǝ������������B���{���͐푈�Œ��������ɏd��ȑ��Q��^�����ӔC��Ɋ����Đ[�����Ȃ��A����3�����d�A�������͔���������B�啽���F�O���͓�����͑����̈Ӌ`�������I���ƕ\���i���ؖ����ɒf����ʍ��j�A�����푈��Ԃ��I�������������퉻����B
- 1972�N10��11���F���h�C�c�ƒ��������������B
- 1974�N10��26���F�u���ؐl�����a���E�k�x�g�i���o�ρE�R����������v�����B
- 1976�N7��28���F�ؖk�n���̓��R�ő�n�k�B����24���l�ȏ�B
- 1976�N10��6���F�]��u4�l�g�v��ߕ߁B1966�N�ȗ��̕�����v�����I���B
- 1977�N7��22���F�������Y�}���]��4�l�g�̓}�����E�i�v�Ǖ��\�B�g�E���������E�B
- 1977�N8��12���F������v���I���錾�B
- 1977�N8��23���F�������Y�}���ŁA���h�E�H�ƁE�_�ƁE�Ȋw�Z�p�́u4�̋ߑ㉻�v��ڎw���V�}�K��\�B
- 1978�N�`�F����������B
- 1978�N12��15���F�A�����J�ƒ����̗��������𐳏퉻�����\�B
- 1978�N12��18���F������11��3������ŕ�����v���̌�����������B
- 1979�N8��11���F�w�l������x���u�ЂƂ���q����v���i�̘_�����f�ځB
- 1980�N9��7���F�؍��N�����C��\���B��C���⎇�z���B
- 1980�N12��22���F�l�����u�ю�Ȃ͕�����v���ʼn߂��v�Ə��߂Ė��w���Ŕᔻ�B
- 1981�N6��29���F�������Y�}��������v����S�ʔے肷��u���j���c�v���̑��B
- 1981�N6��29���F������11��6������ō��Ǝ�ȂɌӗs�M�E�����L��I�o�B
- 1982�N10��7���F���������߂Đ����͂���̃~�T�C�����ˎ����ɐ����B
- 1982�N12��4���F�S���l����\�҉�c�ŁA���Ǝ�ȕ����Ȃǂ̐V���@�̑��B
- 1984�N12��19���F�T�b�`���[�E�C�M���X���⎇�z�E�������A1997�N�̍��`�Ԋҋ���ɒ���B
- 1985�N9��30���F�k����w�ŁA�����_�Ќ����Q�q�ɔ�����w���f���B
- 1986�N10��30���F�k���ɒ������̊�����Ђ��a���B
- 1986�N12��5���F�����E���J�ȂŊw���f���B��C�E�k���E�V�Âɔg�y�B
- 1987�N1��6���F�w�����剻�^�����n�܂�B
- 1987�N1��16���F�w���f���Ȃǂ̐����I�ӔC���Ƃ��āA�ӗs�M���������Y�}�����L�����C�B�⎇�z�������L��s�ɁB
- 1989�N�F�Z�l�V���厖���B
- 1989�N6��23���F�������Y�}���A�����ϑ�����⎇�z�E�����L����C�B��C�ɍ]�����Lj��B
- 1989�N6��26���F��C�x�O�ŋ}�s���q��Ԃ����j�����B20�l���S�B
- 1990�N1��11���F�������{���V���厖���ȗ�8�����Ԃ�ɖk�����S���̉����߂������B
- 1990�N10��20���F�����O���Ȃ����A���a���͖@�Ăɋ������O��\���B
- 1991�N12��15���F�������̌����E�R���q�͔��d�����ғ��B
- 1991�N12��29���F�j�g�U�h�~���̎Q��������B
- 1992�N8��24���F�؍��ƍ��������̋��������B
- 1996�N7��29���F�������ʎZ45��ڂ̒n���j�������s���u����͒�~�v�Ɣ��\�B
- 1998�N1��10���F�͖k�Ȗk����M6.2�̒n�k�B����50�l�A��Ў�54���l�B
- 1998�N6��27���F�N�����g���đ哝�̂��k����K��B
- 1999�N7��22���F�������{���u�@���v��@���B�ȍ~�A�e�����n�܂�B
- 1999�N12��20���F�|���g�K���������̃}�J�I�̍s���������ؐl�����a���֕Ԋ҂���A�}�J�I����ʍs����ɂ��邱�ƂɂȂ�B
- 2002�N7��21���F�������̃_�C�G�b�g��������{�l���������S�B
- 2004�N8��7���F�k���̃T�b�J�[�A�W�A�J�b�v�œ��{���D���B�����l�t�@�������������B
- 2004�N9��19���F�]�������R���ψ����Ȃ�ނ��A�Ӌѓ����������Y�}�A���{�A�R�̑S���������B
- 2004�N10��19���F����3��A���P�b�g�ŐÎ~�C�ۉq���u���_2��C�v��ŏグ�B
- 2005�N�F�����ƕ����@�����B
���ؐl�����a���̕���
- ���V�A�A�J�i�_�ɂ��Ő��E��3�Ԗڂɑ傫�ȍ��B�M�l�X�u�b�N�ɂ��ł���������̍��ƍ�����ڂ��Ă��鍑�ł�����B���E�ő�̐l���������ŁA�Ă̐��Y�ʂ����E1�ʁB
- �u���v�́A���E�̒��S�ɂ���A�����Ƃ��₩�ȕ����Љ�Ƃ����Ӗ��ł���A���X�͉��͕������˂̒n�Ƃ���錻�݂͓̉�Ȃ̂�������w�������t�ł������B���݂ɒ��̉͂��Ƃ��Ɛ��E�̒��S�̉āi�Ñ�̉����j�Ƃ����Ӗ��̒��Ă������B
- �����̖����̕��ނ́A���{�����{����u�������ʍH��v�ɂ���Č��肳��邽�߁A�e���������������������ʂ̖������Ǝv���Ă��Ă����������ɂ��ꂽ��Ⴄ�����ɂ��ꂽ�肷�鎖�������N���肤��B�܂��A�u�����ʖ����v�����݂��Ă���B
- �k���̕����i�k����j����b�Ƃ��Ď�̉��������������ʘb��W����Ƃ��Ă���B����������ł����Ă��A�L����╟����Ȃǂ̕�������������A�L����╟����Ȃǂ͔��ɂ�������Ă���̂ŁA�����ȗ��A�k���l�ƍL���l�ł͂قƂ�lj�b���ʂ��Ȃ����������B���̈זk�����ӂŘb����錾�t��k����A�L���Řb����錾�t���L����ȂǂƂ��Ă���B�������A�����ȗ��̋��炨��ѕ������̕��y�ɂ��A��Ɏ�N�w�ɂ͕��ʘb��b���Ȃ��҂͏����Ȃ����B���A���`�ł͖k����Ƌ��ɍL���ꂨ��щp������p��ƂȂ��Ă���B�܂��S��ł̓|���g�K������g����B�`�x�b�g�A�E�B�O���Ȃǂ̊e���������͂��ꂼ��̌ŗL�̌�����g�p���Ă��邪���p��͖k����B���{�͏��������̌���d����p���������Ȃ���A���w�Z�ȏ�̍�������͌����Ƃ��ď��������̌���͎g�p�����k����݂̂ŋ�����s�Ȃ����ƂȂǂɂ��A�k����y�����鐭�������Ă���B
- ���@�ɏ@���̐M�̎��R���K�肳��Ă���Ƃ͂����A�@�����������{�⋤�Y�}�ɋK���E�}������Ă���X���͔ۂ߂Ȃ��B�����N�҂ւ̏@������͋֎~����Ă���B���ɕ�����v���̎����ɂ͏@�����O��I�ɔے肳��A����⎛�@�E�@���I�ȕ��������j�ꂽ�B�`�x�b�g�ł͕������n�����ꂽ��m���������E�E�Q���ꂽ�肵���Ƃ�����B�������Y�}�́u�O�������ψ���v��ʂ��đS���̏@���c�̂����A�����̏@���c�̂́u���v�̔C���͓}�̔F���K�v�B�`�x�b�g�����A�L���X�g���₻�́u�n������v�A�V���C���W�c�u�@���v�Ȃǂ̒e�������͂悭����Ă���B
- 10��1���͍��c�߂ŏj���B1949�N�A���ؐl�����a���������������Ƃɂ��ȂށB
- ��C���͋@�\�������B
- ���ۘA�����S�ۏᗝ������C��������1�B
- �A�W�A�����m�o�ϋ��͉�c�iAPEC�j�������B
���y�[�W�쐬�ɂ�����A�Q�l�ɂ����Ă���������\�[�X
���̃y�[�W�Ɋւ��邲�ē�
-
���̕�����
Key����
�����W�A
�n���A
���A
���A�W�A�ƃ����N��H��ƁA���y�[�W
���ؐl�����a���ɒH�蒅���܂��B
- Site map��肱�̃T�C�g�̑S�̓I�ȍ\����c���ł��܂��B
- ������肱�̃T�C�g���ɂ���C�ӂ̃L�[���[�h���܂�����T�����Ƃ��ł��܂��B
- ���̕�����URI��
https://www.7key.jp/data/country/e_asia/chn.html�ł��B
Copyright (C) 2007 ���� key@do.ai ���ŁF2007�N03��05�� �ŏI�X�V�F2007�N04��02��