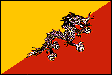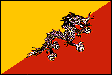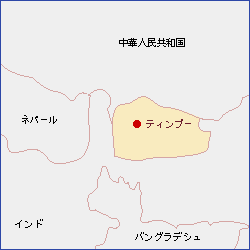ブータン
ブータンの基本情報
- 最終更新
- 2007-04-12T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/s_asia/btn.html#basic
- 国・地域名(ISO 3166-1による英語名)
- ブータン王国【Bhutan】。公式の英語表記は、Kingdom of Bhutan。
- 首都
- ティンプー【Thimphu】
- 国旗
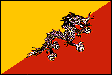
- 人種
- チベット系(約60%)、ネパール系(約20%)等
- 言語
- ゾンカ語、英語、ネパール語(以上公用語)
- 宗教
- チベット仏教(国教)、ヒンドゥー教等
- 通貨
- ニュルタム:Ngultrum(BTN)、インド・ルピー:Indian Rupee(INR)
- 3文字国名コード/2文字国名コード/数字国名コード
- BTN/BT/64
- 人口/面積
- 2,185,569人/47,000平方キロメートル(九州の約1.1倍)
- 国歌/国花/国鳥
- 雷龍の王国/メコノプシス=ホリドゥラ/ワタリガラス(カラス科)
- 漢字による表記
- 不丹
- 時間帯
- UTC +6(DST: なし)
- ccTLD
- .BT
- 国際電話番号
- 975
ブータンのその他情報
- 最終更新
- 2007-04-12T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/s_asia/btn.html#other
ブータンの地形
南アジア、ヒマラヤ山脈の南麓に位置し、東・西・南をインドと、北を中国のチベット自治区と接する内陸国。中国との国境の大部分はヒマラヤ山脈の上を走り、国境線が確定していない部分が多く、国境画定交渉が現在も進められている。国土の標高差は南部の100mから北部の7,561m。国内最高峰はガンカー・プンスム(7561m)。ブラマプトラ川の支流が作る渓谷が居住地。最南部には低地があり、ドワールとよばれる密林が広がっている。
ブータンの気候
標高3000m以上の北部ヒマラヤ山脈の高山・ツンドラ気候、標高1200〜3000mの中部のモンスーン気候、標高1200m未満の南部タライ平原の亜熱帯性気候が並存する。南部は5〜9月の南西モンスーンの影響で雨量が多く、年間4000〜5000mmの降水量がある。
ブータンの経済
主要産業はGDPの約35%をしめる農業だが、最大の輸出商品は電力。国土がヒマラヤの斜面にあることを生かし、豊富な水力による発電を行いインドに電力を売却することにより外貨を得ている。農業では米と麦が栽培され、牛、豚、山羊、ヤクが飼育されている。食糧は自給されている。観光業は有望だが、文化・自然保護の観点からハイエンドに特化した観光政策を進めており、フォーシーズンズなどの高級ホテルの誘致に成功。ただし、外国人観光客の入国は制限されており、バックパッカーとしての入国は原則として不可能。必ず旅行会社を通しガイドが同行する必要があるが、治安の悪い南部地域への渡航制限を除き、自由旅行が禁止されているわけではない。1959年からインドと結ぶ自動車道路が建設され、国王の指導下で慎重に近代化が進められている。
主要貿易品目
輸出は電力、鉱物製品、農林製品。輸入は自動車、自動車部品、コンピュータ、機械製品。
主要貿易相手国
輸出はインド95%、バングラデシュ4%。輸入はインド75%、シンガポール13%、日本、タイ。
ブータンの歴史
- 627年:パロのキチュ・ラカンとブムタンのジャンパ・ラカンがソンツェン・ガンポによって建設される。
- 747年:パドマサンババがチベット仏教ニンマ派を伝える。
- 1616年:チベット仏教カギュ派ドゥク支派に内紛があり、チベットを逃れた同派の管長シャブドゥン・ガワン・ナムゲルがこの地の支持者に迎えられて建国。
- 1626年:イエズス会のポルトガル人神父、エステヴァン・カセラ、ヨハン・カプラルがヨーロッパ人として初めてブータン入国。
- 1864年:イギリス=ブータン戦争(ドゥアール戦争)勃発。
- 1865年:ドゥアール戦争に敗北し、イギリスとの間にシンチュラ条約を締結。イギリスからブータンに年5万ルピーが補助金として支払われることになる。
- 1907年:ワンチュク家(現王朝)が支配権を確立。ウゲン・ワンチュクが初代国王となる。
- 1910年:プナカ条約締結。チベットから分離。イギリスの保護下に入る(1949年まで)。
- 1926年:ジグミ・ワンチュクが第2代国王になる。
- 1949年8月8日:インド・ブータン条約調印。
- 1952年:ジグミ・ドルジ・ワンチュクが第3代国王になる。
- 1964年:ジグミ・パルデン・ドルジ首相が暗殺される。
- 1972年:国際連合に加盟。ジグミ・シンゲ・ワンチュクが第4代国王になる。
- 1974年:第4代国王戴冠式。
- 1990年:反政府運動激化。南部居住のネパール系住民が国外に脱出し難民化する。
- 1999年:国内テレビ放送開始。
- 2005年:ワンチュク国王、08年の譲位と総選挙後の立憲君主制移行を表明。
- 2006年:当初の予定をくり上げて、ジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュクが第5代国王に即位。
ブータンの文化
- 世界唯一のチベット仏教を国教とする王国。17世紀に移住したチベットの高僧ガワン・ナムゲルが、現在の国土をまとめた。
- 英語が事実上の第一公用語であり、全ての法令、公文書は英語で書かれている。ほぼすべての教育機関が英語を教授言語としている。唯一の活字メディアであるクエンセル紙は、英語、ゾンカ語、ネパール語で発行されているが、購読者が最も多いのは英語版。英語の公用語化は最近始まったため、中年以上の世代にはあまり通じないとされる。英語教育を受けた若い世代には英語をもっぱら第一言語とし国語であるゾンカ語を話せても読み書きができない者もいる。また、地方の少数民族を中心にゾンカ語を話せない人も多く、ブータンで最も通用性が高いのはヒンディー語やそれに類するネパール語であるとされる。国内の言語分布は、西部はゾンカ語、東部はツァンラカ語(シャチョップカ語)、南部はネパール語が主要言語。
- 急速な近代化(欧米化)の中で、近代化の速度をコントロールしつつ独自の立場や伝統を守ろうとする政治に世界的な注目が集まっている。現国王が提唱する国民総生産にかわる国民総幸福量(GNH)という概念、様々な環境政策、伝統文化保持のための国民に民族衣装着用の強制などが、近年のスローライフなどのキーワードと組み合わされて語られる場合も多い。
- ブータンはイギリス領インドとの条約に「内政は不干渉、外交には助言を与える」という文言が存在し、1949年のインド=ブータン条約にその文言が継承され、多額の補助金がブータンに付与されていたためインドの保護国的な印象を受けるが、公的には1907年をもって国家成立としている。
- 国樹はイトスギ、国獣はターキン。
- 2004年12月より、環境保護及び仏教教義的な背景から世界初の禁煙国家となり、煙草の販売が禁止された。国外から持ちこむことは出来るが、100%の関税が課せられる。
- 首都ティンプーは標高2400mの高地に位置する。高山ばかりがそびえているためか、ブータンでは山に名前を付けない。
当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
地理、
国、
南アジアとリンクを辿ると、当ページ
ブータンに辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/country/s_asia/btn.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年03月05日 最終更新:2007年04月12日