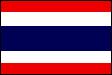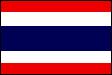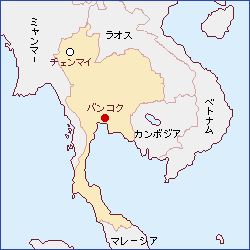タイ
タイの基本情報
- 最終更新
- 2007-03-28T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/es_asia/tha.html#basic
- 国・地域名(ISO 3166-1による英語名)
- タイ王国【Thailand】。公式の英語表記は、Kingdom of Thailand。
- 首都
- バンコク【Bangkok】
- 国旗
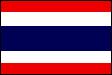
- 人種
- 大多数がタイ族。その他、華僑、マレー族、山岳少数民族等。
- 言語
- タイ語(公用語)
- 宗教
- 仏教95%、イスラム教4%。
- 通貨
- バーツ:Baht(THB)
- 3文字国名コード/2文字国名コード/数字国名コード
- THA/TH/764
- 人口/面積
- 64,865,523人/514,000平方キロメートル(日本の約1.4倍)
- 国歌/国花/国鳥
- タイ国歌/国王賛歌/ナンバンサイカチ/シマハッカン
- 漢字による表記
- 泰
- 時間帯
- UTC (+7)(DST: なし)
- ccTLD
- .TH
- 国際電話番号
- 66
タイのその他情報
- 最終更新
- 2007-03-28T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/es_asia/tha.html#other
タイの地形
東南アジアに位置し、東にカンボジア、北にラオス、西にミャンマーとアンダマン海があり、南はタイランド湾とマレーシアがある。国土はインドシナ半島の中央部とマレー半島の北部。タイは大きく4つの地域に分けられる。北部は山岳地が広がり比較的涼しい気候。タイ国内最高峰であるドーイ・インタノン(2,576m)もこの地域にある。東北部はほぼ全域にコーラート台地が広がり、雨量が少なく農作物が育ちにくい環境にあって、貧困地域の代表格にもなっている。中央部にはチャオプラヤー(メナム)川が形成したチャオプラヤー・デルタと呼ばれる豊かな平地が広がり、世界有数の稲作地帯を作り出している。尚、チャオプラヤー川は国土を南北に貫流し、首都バンコクにも流れている。南部はマレー半島の一部で、雨期が中央部よりも長いことで有名。ラオスとの国境にはメコン川が流れる。タイ西部アンダマン海にはプーケット島があり、国際的なリゾート地として有名。
タイの気候
熱帯性に属しモンスーンの影響が大きい。5月中旬から10月にかけては空気が湿り、なま暖かく、スコールなどを特徴とする雨期に見舞われる。特に9月と10月は降雨量が多く、洪水が起こることもある。11月から3月中旬までは雨が少なく、比較的涼しい乾期となる。特に12月頃には寒季。4月には暑季と呼ばれる非常に暑い気候となり、夏を迎える。
タイの経済
労働人口半分以上が農業に従事し、メナム川流域では米、高原ではトウモロコシやサトウキビ、半島ではゴム、タピオカなどを生産する。養殖エビなどの水産、養鶏、野菜栽培も盛ん。山林が荒廃したために伐採は原則として禁止されている。地下資源ではスズ、鉄鉱石、タングステンを産出。天然ガスの採掘が開始され、エネルギー輸入の負担が減少した。工業は食品加工、繊維などの軽工業が中心だが、1970年代から日本やアメリカの企業が進出し、電機、電子産業など輸出産業が急成長し高度経済成長の段階に入った。しかし1996年、輸出が不振となると不良債権問題が表面化し、バブル化した経済が崩壊、アジア通貨危機を招いた。この危機は特にタイの財閥の同族支配廃止や、外国資本の参入につながった。この後、外国への輸出を積極的に行ったことから1999年、経済成長率は再び4%台を記録、2003年には6%台を記録し、タイは好景気に逆転した。また、タイは観光地として世界的に人気が高く、特に北半球が冬となる12月から2月にかけては世界中の国々からの観光客で賑わいをみせ、観光産業は大きな外貨獲得手段の1つとなっている。
主要貿易品目
輸出はコンピューター、自動車・部品、集積回路、天然ゴム。輸入は原油、機械・部品、電気機械・部品、化学製品。
主要貿易相手国
輸出はアメリカ、日本、中国、シンガポール、香港。輸入は日本、中国、アメリカ、マレーシア、アラブ首連。
タイの歴史
- 1238年:タイ王国の基礎となるスコータイ王朝が成立。タイ語のアルファベットであるタイ文字が完成したのは、3代目ラームカムヘーン大王の時代。
- 1350年:アユタヤー王朝。
- 1767年:トンブリー王朝
- 1782年:チャクリー王朝(現在の王朝)。
- 1932年6月24日:人民党によってクーデターが勃発。絶対君主制から立憲君主制へと移行(民主革命、立憲革命)。
- 1940年12月23日:日本とタイが和親友好条約を批准・交換(6月12日調印)。
- 1941年7月10日:日・仏・タイ和平条約が公布される。
- 1941年12月21日:日本とタイが軍事同盟条約に調印(日泰攻守同盟条約:即日実施)。
- 1942年1月8日:イギリス軍がバンコクを爆撃したのを機に同月25日、ピブーンソンクラームは中立政策を完全に翻しイギリスとアメリカに宣戦布告。
- 1943年12月25日:ビルマとタイを結ぶ泰緬鉄道が日本軍の建設により開通。
- 1944年頃:日本の敗色が濃くなるとプリーディーが「自由タイ」を指揮するなど急速に連合国との関係を強める。
- 1945年8月:日本が連合国に対して敗北すると、プリーディーは「タイの宣戦布告は無効である」と宣言し、連合国との間の敵対関係を終結させようとした。こうした巧妙な政治手腕により、タイは連合国による敗戦国としての裁きを免れた上に、国際連合での敵国条項にその名を連ねることも無かった。
- 1946年12月16日:国連加盟。
- 1953年9月4日:「日・タイ通商条約」調印。
- 1967年:東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟。
- 1989年:アジア太平洋経済協力会議(APEC)に加盟。
- 1992年5月:流血革命が発生するも、プーミポン現国王の仲裁により収まる。
- 1997年7月2日:タイ政府によるタイバーツの変動相場制導入により、アジア通貨危機が始まる。
- 1997年:アジア通貨危機により経済は一時的に停滞。
- 2006年9月16日:ソンクラー県ハートヤイで同時多発爆弾テロ事件が発生。外国人を含む5人が死亡、68人が負傷。
- 2006年9月19日:軍事クーデター勃発。ニューヨークを訪れていたタクシン首相が非常事態宣言を発表するも、軍部はこれを無効とし、タイ全土に戒厳令を発布。
- 2007年1月1日:バンコクで連続爆弾テロが8件起こる。
タイの文化
- かつては諸外国から、Siam(シャム、サイアム)と呼ばれており、公式名称としても使われていた。しかし、1949年5月11日、タイ人の民族名であり、タイ語で「自由」を意味するThai(タイ)に改めた。この名称は、東南アジア諸国が列強諸国の植民地となる中、タイが独立を保ったことを示している。ただし、「タイ」という言葉が自由という意味として使われることは一般的ではなく、タイ国民も「タイ」をこの意味で使うことは稀だという。
- 伝統的に王室メンバーへ対しての国民の敬意が非常に高く、国王や王妃の誕生日には国中が誕生日を祝うお祭り状態となり、誕生日の前後には国民が自ら作成した肖像が国中に飾られる。
- トムヤムクンやパッタイなどのタイ料理は世界的にポピュラーであり、そのスパイシーかつバラエティに富む味と健康的な素材が日本を始めとする多くの国で高い人気を誇る。
- 現王朝の初代王ラーマ1世(チュラーローク将軍)は1782年に首都をトンブリーからバンコクに移したため、バンコク王朝とも呼ばれる。また、バンコクの非常に長い正式名称にも含まれているタイの守護仏の名から、ラッタナーコーシン王朝とも呼ばれる。
- タイでは朝の8時と夕方の6時、駅や学校など人の集まるところで国歌が流れるが、第2国歌ともされるほど国民に親しまれている『国王賛歌』があり、各種式典や映画の上映前などに流されている。最初に曲が作られたのはスローバラード調の『国王賛歌』とされ、1800年代後半にオランダのヘーウッドセーンとの作曲家に依頼、タイの古典曲を加味して完成させたとされる。一方『国歌』とされる元気がよくリズミカルな曲は、1939年に国名がシャムからタイに改められたのをきっかけに作詞コンテストを開いて決められたとされる。
- 東南アジア諸国連合加盟国。
- アジア太平洋経済協力会議(APEC)加盟国。
当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
地理、
国、
東南アジアとリンクを辿ると、当ページ
タイに辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/country/es_asia/tha.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年03月05日 最終更新:2007年03月28日