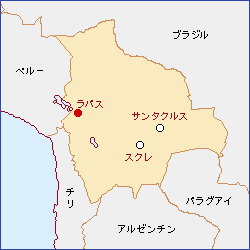ボリビア
ボリビアの基本情報
- 最終更新
- 2007-04-17T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/s_america/bol.html#basic
- 国・地域名(ISO 3166-1による英語名)
- ボリビア共和国【Bolivia】。公式の英語表記は、Republic of Bolivia。
- 首都
- ラパス【La Paz】(憲法上の首都スクレ【Sucre】)
- 国旗

- 人種
- インディオ55%、混血32%、欧州系13%
- 言語
- スペイン語、ケチュア語、アイマラ語、グアラニー語(以上公用語)
- 宗教
- カトリック95%、プロテスタント(国教はカトリックだが信仰の自由も認められる)
- 通貨
- ボリビアーノ:Boliviano(BOB)
- 3文字国名コード/2文字国名コード/数字国名コード
- BOL/BO/68
- 人口/面積
- 8,724,156人/1,098,580平方キロメートル(日本の約3倍)
- 国歌/国花/国鳥
- ボリビアの国歌/カンツータ/-
- 漢字による表記
- 暮国/暮利比亜/保里備屋/玻里非/玻利維亜
- 時間帯
- UTC -4(DST: なし)
- ccTLD
- .BO
- 国際電話番号
- 591
ボリビアのその他情報
- 最終更新
- 2007-04-17T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/country/s_america/bol.html#other
ボリビアの地形
南アメリカ大陸に位置し、北と東はブラジル、南はアルゼンチンとパラグアイ、西はチリとペルーと国境を接する内陸国。西部は6000m級の高峰がそびえるアンデス山脈、ラパス市・オルロ市にかけて標高4000mくらいの広大な平らな土地が広がり、この地域はアルティプラーノと呼ばれる。中央はアマゾン川上流の渓谷地帯を持つ高原。北東から東にかけてはアマゾンの熱帯地域であり、リャノ【llano】またはオリエンテ【oriente】と呼ばれる。リャノはさらに熱帯雨林が広がる北側と、乾燥し大草原地帯であるグランチャコ地方(パラグアイ国境ちかく)とに分かれる。ペルーとの国境には航行できる湖としては標高が最も高いチチカカ湖(3812m)がある。
ボリビアの気候
東部低地は熱帯気候で雨季と乾季に分かれ、11〜3月が雨季。中西部は寒冷な高山気候だが、標高の低い土地は温和。アマゾン川流域の低地では高温多湿の熱帯性気候もみられる。
ボリビアの経済
農業は就業人口の半数近くを占め、サトウキビやジャガイモを栽培し、羊、牛、アルパカを飼育する。ほとんどは零細な自給農業で生産性が低く、主要な産物以外は輸入に依存する。2006年5月16日、ガルシア副大統領より「第二次農地改革」計画案が発表され、生産的でない土地及び国有地を農民や先住民に分配。地下資源が豊富で、スズ、鉛、アンチモン、タングステンなどを産出。特にスズは世界有数の産地。1970年頃から石油と天然ガスの産出量が増加し、国内需要を満たすだけでなく輸出も行われるようになった。2006年1月、生産や、輸送、販売を含め天然ガスを国有化。製造業は食品加工と国内向けの軽工業程度。全輸出額を上回るともいわれる密輸麻薬の原料、コカの栽培が問題にもなっている。
主要貿易品目
輸出は宝飾品、金、亜鉛、大豆、錫、木材、砂糖、天然ガス、亜鉛、鉛、銀、大豆、木材、ブラジリアンナッツ。輸入は機械、鉄鋼、自動車、電気製品。
主要貿易相手国
輸出はブラジル、コロンビア、アメリカ。輸入はブラジル、アメリカ、アルゼンチン、チリ。
ボリビアの歴史
- 紀元前1500年頃:チリパ文化が栄える。
- 5〜12世紀頃:ティワナク文化が栄える。
- 12世紀頃から:チチカカ湖沿岸にアイマラ諸王国が栄える。
- 1470年頃〜1532年:アイマラ諸王国がインカ帝国に編入される。インカ帝国内にてアイマラ諸王国は継続。
- 1532年:インカ帝国崩壊。スペインによる植民地化が始まる。
- 1535年:フランシスコ・ピサロによりペルー副王領が作られる。
- 1545年:ポトシ銀山発見。過酷な労働と病気でインディオは次々に死んでいった。
- 1559年:チャルカス(現スクレ)に聴問庁設置。この頃、現ボリビアの地域は「アルト・ペルー(高地ペルー)」と呼ばれる。
- 1776年:ペルー副王領からラ・プラタ副王領に転入。スペイン本国生まれの少数支配に反対して土着のスペイン人による独立運動が起こる。
- 1781年:アイマラによる反乱蜂起(トゥパク・カタリの暴動)。
- 1809年:チュキサカでクリオーリョによる独立運動(ボリビア最初の独立運動)。
- 1823年:独立戦争始まる。
- 1825年8月6日:シモン・ボリバルの協力により将軍アントニオ・ホセ・デ・スクレがアルト・ペルーをスペインから独立させる。
- 1879年:ペルーと同盟を組みチリに宣戦布告(太平洋戦争)。
- 1884年:チリに敗北。バルパライソ条約で海岸の領土を失い、内陸国になる。
- 1899〜1903年:ブラジルと紛争(アクレ紛争)。結果敗北してアクレ地方をブラジルに割譲。
- 1932年:パラグアイに宣戦布告(チャコ戦争)。
- 1938年:チャコ戦争終結。ブエノスアイレス講和条約によりチャコ地方がパラグアイの領土となる。
- 1945年11月14日:国連加盟。
- 1951年:民族主義的革命運動党(MNR)が大統領選に勝利するも、クーデターにより軍部に政権を奪われる。
- 1952年4月:鉱山労働者らの武装蜂起。MNRによる政権樹立。パス・エステンソロが大統領に就任(4月革命)。
- 1964年:軍によるクーデター。軍部と共産党の対立が進む。
- 1967年:チェ・ゲバラがゲリラ戦の末死亡。その後、軍とMNRなどの政権争いやクーデターが続く。
- 1982年:民政復帰。この頃から激しいインフレが起こる。
- 1986年:100万分の1のデノミで8,000%超のインフレを抑制。
- 1990年:この年代の中頃に天然ガス田が発見。
- 2000年:コチャバンバ水紛争。
- 2003年:ボリビアガス紛争。
ボリビアの文化
- 国名はラテンアメリカの解放者として知られるシモン・ボリバルにちなんで名付けられた。
- ラパスは、立法府・行政府の所在地。スクレは、憲法上の首都であり、司法府(最高裁判所)の所在地。
- 首都ラパスは世界で一番標高の高いところにある首都として知られる。
- 建国当初のボリビアは、現在よりもはるかに広い領土を持っていたが、チリ、ブラジル、パラグアイとのそれぞれの戦争に負け大きく領土を割譲している。特に、かつては太平洋に面する領土を保有していたが、チリとの戦いに敗れて海岸線を全て失ったことはボリビアの歴史上重要な点である。ボリビアでは今もなおこのことでチリに恨みを持つ人が多く、3月23日を「海の日【dia del mar】」として「海を取り戻そうキャンペーン」を行っている。
- 港を持たないボリビアの海運での輸出入貨物はチリの港で陸揚げされている。 チリにはボリビアが管理する保税上屋があり、一種の治外法権のように港の一部をボリビアが管理している。ボリビアの保税上屋に荷揚げされた貨物に対してはチリ側は関税を課さないことになっており、陸揚げされた貨物は保税状態のままチリ国内を鉄道やトラックを使ってボリビアへ運ばれ国境で関税の手続きを行うことになっている。
- メスティーソのうち伝統的な衣装を身に着けている女性はチョリータと呼ばれる。彼女らの格好はボリビアを特徴づける習俗となっている。
- スペイン語、ケチュア語、アイマラ語、グアラニー語が公用語。田舎ではケチュア語、アイマラ語、グアラニー語が用いられているが、スペイン語を全く解さない人は近年少なくなってきている。都市部ではスペイン語以外の言葉を話せない人の方が多い。
- プレ・インカやインカ帝国の文明圏、スペイン統治下のペルー副王領の勢力圏など、ペルーとボリビアはほぼひとまとまりの地域として扱われてきたため、現在でも文化的にきわめて近い関係にある。ちなみにチョリータも両国に共通する特徴的な習俗である。
- アンデス地域とアマゾン地域はその気候の大きな違いや町の起こりの経緯の違いにより、互いに文化的な差異を感じているとされる。アンデス地方の町の多くはインカ帝国時代の集落がペルー副王領時代に町として興されたものであるのに対し、アマゾン地域の町はパラグアイ方面から開拓されていったものが多い。俗語で、アンデス地域またはそこに住む人々はコージャと呼ばれ、アマゾン地域またはそこに住む人々はカンバと呼ばれる。
- 食文化としては、パン・ジャガイモ・トウモロコシを主食とし、副食として主に牛肉・鶏肉を食べる。豚肉は高級な食材とされる。クイと呼ばれる天竺鼠の一種も食用としている。ボリビアは海を持たないため海産物の食文化は持たないが、それ以外は食文化についてもペルーとあまり違いがない。
- 南米南部共同市場(メルスコール)準加盟国。
当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
地理、
国、
南アメリカとリンクを辿ると、当ページ
ボリビアに辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/country/s_america/bol.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年03月05日 最終更新:2007年04月17日