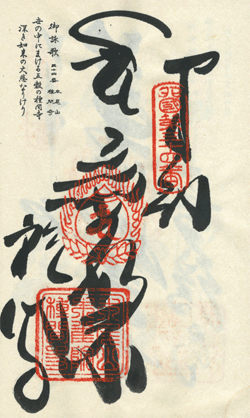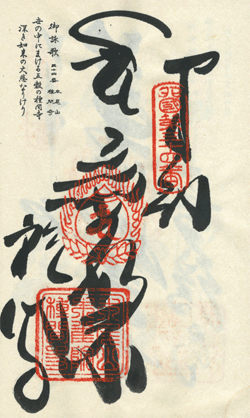第34番札所 本尾山種間寺
本尾山種間寺の基本情報
- 最終更新
- 2007-05-21T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/shikoku88/s34_tanemazi.html#basic
- 正式名称と通称
- 本尾山朱雀院 種間寺(もとおざん たねまじ)/通称:-
- 本尊と宗派、開基
- 薬師如来 / 真言宗豊山派 / 弘法大師
- 真言
- オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ
- 御姿
-


- 御詠歌
- 唱え奉る 四国霊場 第34番 本尾山 種間寺 の御詠歌に
- 世の中に 蒔ける五穀の 種間寺 深き如来の 大悲なりけり(よのなかに まけるごこくの たねまでら ふかきにょらいの だいひなりけり)
- 所在地と電話番号
- 〒781-0321:高知県吾川郡春野町秋山72(088-894-2234)
- 前札所と次札所
- 前札所:第33番札所 雪蹊寺(6.3km)/次札所:第35番札所 清瀧寺(9.5km)
- 交通と駐車場
- 徒歩:雪蹊寺→諸木駐在所→春野村役場→種間寺
- 雪蹊寺から徒歩1分、高知県交通バス春野村役場前新川通り行:雪蹊寺前→春野役場前(27分)
- JR高知駅下車。はりまや橋から秋山又は春野行きバス40分(種間寺下車)。徒歩3分。
- 駐車場:無料(15台:境内まで徒歩2分)
- 宿泊
- なし
本尾山種間寺のその他情報
- 最終更新
- 2007-05-21T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/shikoku88/s34_tanemazi.html#other
歴史と謂れ
敏達天皇の6年(577年)、摂津の四天王寺造営のために来日した百済の仏師寺匠が、帰国の途中に土佐沖で暴風雨におそわれ、避難しようと秋山の郷に寄港した。そして海上安全を祈って刻んだのが薬師如来で、本尾山の頂きに安置したとされる。やがて弘法大師がこの地へ巡錫し、その薬師如来を本尊として寺を開創、中国から持ち帰った五穀(米・麦・栗・きび・豆)の種子を撒いたとされる。種間寺の寺名はこれにちなむ。その後も寺は栄え、天暦年間には村上天皇が藤原信家を勅使として下向、藩政時代には土佐藩主の山内公からも厚い信仰を受けた。明治初期の神仏分離で一時的に廃寺となるが、明治13年(1880年)には再興した。
堂塔
種間寺には山門がなく、境内は細長く延びている。本堂が奥に建てられ、右手に大師堂、左手には子育て観音が祀られている。観光客とは無縁で静かな札所。
本堂
伽藍は全て、昭和45年の台風後に再建された。それ以前は歴史のある堂宇が並んでいたが、今はモダンな堂宇となっている。本堂も明るく、色鮮やか。
子育て観音
行事
-
その他の情報
- 百済の仏師が彫ったといわれる薬師如来像は、国宝に指定されている。旧暦の1月21日は一般に御開帳される。また、安産の薬師としても信仰され、妊婦は柄杓を持参して祈願する。寺ではその柄杓の底を抜き、三日の間ご本尊に祈祷してお札とともにかえし、それを妊婦は床の間にまつり、安産すれば柄杓を寺へ納めるという。柄杓の底を抜くのは「通りがよくなる」からで、安産に通じるとのこと。
- 種間寺の奥之院は海岸近くにあり、こちらにも薬師如来が祀られている。
- 本堂の右脇にある手水鉢は延宝5年(1677年)のもので、町内最古のものといわれる。
- 藤原信家が勅使として下向し、種間の勅額を奉納した際の話。大般若経600巻を書き写して奉納しようとしたが、どこからともなくお坊さんが現われ、「あなたの願いをかなえよう」と言い、信家に代わって3年3か月をかけて写経を行った。般若経を納めようとした時、にわかに大嵐が吹いて600巻の般若経は空高く巻き上げられ、しばらくして舞い降りた時にはお経の文字がすっかり消えていたとの話が残っている。願主である信家自身が書いたものでないので返されたのだろうが、このため「白字大般若経」とも言われ、朝廷に奉納されたと伝わっている。
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
思想、
四国霊場八十八箇所とリンクを辿ると、当ページ
第34番札所 本尾山種間寺に辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/shikoku88/s34_tanemazi.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年05月21日 最終更新:2007年05月21日