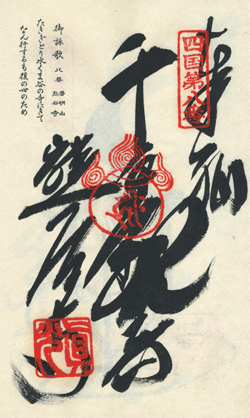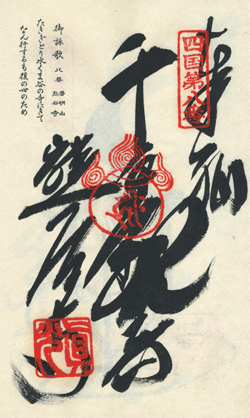第8番札所 普明山熊谷寺
普明山熊谷寺の基本情報
- 最終更新
- 2007-05-21T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/shikoku88/s08_kumatanizi.html#basic
- 正式名称と通称
- 普明山真光院 熊谷寺(ふみょうざん くまたにじ)/通称:-
- 本尊と宗派、開基
- 千手観世音菩薩 / 高野山真言宗 / 弘法大師
- 真言
- オン バザラ タラマキリク
- 御姿
-


- 御詠歌
- 唱え奉る 四国霊場 第8番 普明山 熊谷寺 の御詠歌に
- 薪とり 水熊谷の 寺に来て 難行するも 後の世のため(たきゞとり みずくまだにの てらにきて なんぎょうするも のちのよのため)
- 所在地と電話番号
- 〒771-1506:徳島県阿波市土成町字前田185(088-695-2065)
- 前札所と次札所
- 前札所:第7番札所 十楽寺(4.2km)/次札所:第9番札所 法輪寺(2.4km)
- 交通と駐車場
- 徒歩:十楽寺→高尾谷橋→御所大橋→参道曲り角タバコ屋→熊谷寺
- JRバス鴨島行7番札所前一阿波吉田(3分)、下車後徒歩(1.8km)
- JR徳島線鴨島駅下車。市場行きバス9分(北二条前下車)。徒歩1時間。
- 駐車場:無料(50台:境内まで徒歩3分)
- 宿泊
- なし
普明山熊谷寺のその他情報
- 最終更新
- 2007-05-21T00:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/shikoku88/s08_kumatanizi.html#other
歴史と謂れ
弘仁6年(815年)、弘法大師がこの地のやや奥にあたる閼伽ケ谷で修行している際、紀州の熊野権現があらわれ、観世音菩薩の尊像を感得した。そこで大師は結伽趺坐(足の表裏を結んで坐する円満安座)して日夜精進。一刀三礼して霊木に等身大の千手観世音を刻み、その頭髪の中へ仏舎利百二十粒を入れ、胎内に熊野権現から授かった金像を納め、堂宇を建立して安置したといわれる。二重の塔は、安永3年頃、剛意上人が建立したもの。本尊は昭和2年の火災で本堂ともども焼失している。現在のものは昭和47年のもの。
堂塔
山門を入ると右に弁天池、左に庫裡、羅漢堂、多宝塔があり、仁王門から石段を登ると昭和15年再建の本堂になる。左手の大師堂へは更に石段を登る。
- 仁王門

- 貞享4年(1687年)に、中興開山の長意上人が建立した。左右に仁王像が立っている。和式と唐式を折衷した建築で、 高さ13メートル、桁行9メートル、梁間5メートルの三間重層の重厚な構えは四国霊場で最も大きい。県の重要文化財に指定されており、二層目の天井や柱には天女像などが描かれている。
- 本堂
- 大師堂
- 屋根に据えつけられた露盤から宝永4年(1707年)に建立されたことが分かる。
- 多宝塔
- 四国最大最古とされる多宝塔。安永3年(1774年)に建立された。胎蔵界大日如来像を中心に、東に阿閼如来、南に宝生如来、西に無量寿如来、北に不空成就如来が祀られている。
弁天様
納経所前の池に浮かんでいる弁天島の弁天は、元々大師堂の池にあったが昭和6年に移建された。弁天様は安産に霊験があるとされる。
その他
行事
-
その他の情報
- 大師堂に安置されている大師像は永享3年(1431)の作で、寺宝とされ徳島県指定重要文化財の指定を受けている。
- 現在では火災などに遭わないように配慮され、本尊は本堂裏手の別棟に祀られ、本堂から拝むようになっている。
- 現存する大看板「普明山」の額は安政大修理の際に寄付されたもので、裏には「萬延元年、七月 二十日 再興願主 矢部惣左ェ門」と墨書の銘が記されている。
- 昔の言い伝えで、山門の2体の仁王像を十楽寺へ移すことになり、村人が1日がかりで運んだが、夜が明けると仁王像は元の熊谷寺の山門に戻っており、何度運んでも仁王像は戻るので十楽寺に運ぶのをあきらめた、とされる。
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
思想、
四国霊場八十八箇所とリンクを辿ると、当ページ
第8番札所 普明山熊谷寺に辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/shikoku88/s08_kumatanizi.htmlです。
Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年05月21日 最終更新:2007年05月21日